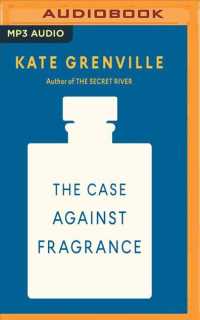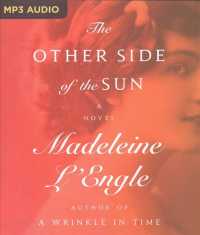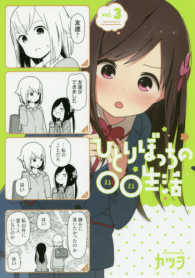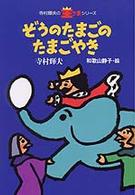出版社内容情報
赤坂 治績[アカサカ チセキ]
著・文・その他
内容説明
歌舞伎の神髄は「名せりふ」にあり―。かつて歌舞伎は娯楽の中心であり、今に残る「名せりふ」は、歌舞伎を支え続けた庶民が培ってきた、日本文化の結晶に他ならない。近松門左衛門から、鶴屋南北、河竹黙阿弥まで。忘れられかけた日本人の心が詰まった四十一の名せりふ。せりふが分かると、歌舞伎がより楽しくなる。巻末に「歌舞伎の台本とせりふ」の概説をつけ、歌舞伎の入門書としても役立つ一冊。
目次
第1章 近松門左衛門
第2章 竹田出雲・並木千柳・三好松洛
第3章 近松半二・菅専助・文耕堂…
第4章 並木五瓶・奈河亀輔・瀬川如皐…
第5章 鶴屋南北
第6章 河竹黙阿弥
著者等紹介
赤坂治績[アカサカチセキ]
1944(昭和19)年山梨県生まれ。演劇評論家。劇団前進座、「演劇界」編集部を経て独立
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
たまきら
43
落語好きな家だったので、歌舞伎は落語を通してちょっとしたセリフを覚えている…といったかんじの私。歌舞伎はあまり興味がなく、能が好きなんですが、夫が借りてきたこの本をめくりながら意外なぐらい聞いたことがある言葉が多いことに気づきました。…夫はめくってもいないんだけど、なんで借りてきたんだろう?2023/07/03
たーぼー
20
歌舞伎に疎い私には基礎知識の解説が実にわかり易く有難かった。そんなライト層の人達にも気軽に手に取れるカジュアルな一冊。収録されている演目も台詞もどこかで耳にしたものが多いはず。歌舞伎の歴史は大衆とともにあり、彼らなしには成立しなかったわけだから馴染みもあるのだろう。それにしても今でも使われる言葉の中には歌舞伎由来のものが結構あるんですね。『こいつは春から縁起がいいわえ(三人吉三廓初買)』とか。『絶景かな、絶景かな(金門五三桐)』って言う人もたまにいますねえ。あらためて日本語の奥深さ美しさを感じました。2015/03/28
あんさん
17
図書館本。七五調と、少しそれを崩した台詞、それに韻を踏んだ掛け言葉は何とも気持ちがいい。あとがきに、現代でいうと歌舞伎はレビュー、人形浄瑠璃は音楽劇要素が強い人形劇とある。リズムが心地良い台詞回しがこれら古典芸能の魅力だろう。2024/02/12
おひゃべりのナオ@【花飛】ヤオイは三月の異名にあらず
10
四分の一の台詞はそらんじてた。解説の半分は要らない。短い台詞がないのが淋しい「してしてどうじゃ」とか「刀も刀」とか「馬鹿めっ」とか「恋する法界坊」とか。2015/01/03
はぴた(半分お休み中)
9
歌舞伎の有名演目の台詞とその解説。改めて字で読むと、どの台詞も素晴らしい。葛西聖司さんの軽いタッチの本「言葉の切っ先」と前後して読んだので、こちらの解説の詳しさが面白かった。ちょっと昔はこういう台詞って誰もが知っていて、ちょいちょい日常的に出てきていたんでしょうね。「死んだはずだよお富さん~♪」って口ずさめる自分がいます。2015/08/29