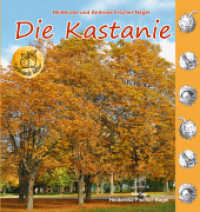出版社内容情報
言った・言わない、SNS炎上、忖度はなぜ起こる? 日常のことばを豊富な例題で解説し、文を構造で捉える視点を授ける実践的案内。
内容説明
「かみ合わない」にさらば!ありそうでなかった言語学ドリル。「言いたいことがうまく言えない」「思うように伝わらない」「相手の意図が分からない」…頭の中の“無意識の言語知識”を明らかにする理論言語学の知見を使い、単語の多義性や曖昧性、意味解釈の広がり方や狭まり方、文脈や背景との関係を身近な例から豊富に解説。文の構造を立体的に掴む視点が自然と身につき、言葉の感覚がクリアになる実践的案内。
目次
第1章 無意識の知識を眺める:意味編(「良い宿がいっぱい」―語句の多義性;「虎を捕まえてみよ」―言葉の不明確性 ほか)
第2章 無意識の知識を眺める:文法編(おかしな文いろいろ;品詞の違いを意識する ほか)
第3章 言葉を分析する(曖昧性を分析する;似た表現の違いを分析する ほか)
第4章 普段の言葉を振り返る(人前に出す文章を添削する;「ちょっと分かりにくい」婉曲表現 ほか)
著者等紹介
川添愛[カワゾエアイ]
九州大学、同大学院他で言語学を専攻し博士号を取得。津田塾大学女性研究者支援センター特任准教授、国立情報学研究所社会共有知研究センター特任准教授等を経て、言語学や情報科学をテーマに著作活動を行う(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
-





akky本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
83
言語学・・何度か、耳にしたことがある分野。何となくのイメージしかない。それもあるが、ふだん使いという言葉に惹かれた。何気なく使っている言葉。話言葉、書き言葉。それを受け取るほうでもある。ここ数年、職場で、特に外部にでる言葉に気を付けるようになった。それを振り返るに、いいタイミングで出合った。まずは、何か違和感を感じるかどうかだろうと思う。そこで、考え直す時間をとることで、随分、わかりやすくなると思う。わかりやすいとは、解釈の幅がシンプルになることかと思う。必然的に、誤解もなくなると思う。2021/04/12
アナーキー靴下
74
言語学者である著者が、理論言語学の視点で日本語についてあれこれ説明してくれる本。期待しすぎたか個人的にはイマイチ。例文を交えて丁寧に説明してくれるのだが、言葉について言葉だけで説明するというのはどうしても冗長な印象。また、おかしな例文は、日本語としての不自然さを読者も感じること前提なのが…おかしいと感じるなら目新しくはなく、感じないなら著者の説明で納得できるのか疑問だ。即効性ではなく基礎力向上、構造的に理解するには役立つので、日本語教師の方など、考えたこともなかった類いの、鋭い質問を受ける人には良いかも。2021/06/29
みき
63
言語は自然的なものであるし地域によっても特性が強い。そんな中でこれを科学的に研究対象とするのであるから学者さんの苦労も伺えようもの。後書きにある筆者の「これは本当に科学と呼べるのか」という問いかけは偽らざる本音でおそらく筆者もそういう自問と戦っていたのだろう。そんな中で言葉の基礎力を鍛えるために言語学の基礎を学んでみよう、言語学の良いとこ取りをして日常に活かしてみようとするコンセプトは非常に面白い。内容も文法から意味的なところまで題名のとおり「普段使い」に言語学の使用方法が解説されている。間違いなく良書。2024/01/22
ネギっ子gen
53
【無意識の知識を眺め、言葉を構造的に捉え、確実に言えていることと言えていないことを区別するのに慣れれば、言葉についての感覚は確実に鋭くなる】単語の多義性や曖昧性、意味解釈の広がり方や狭まり方、文脈や背景との関係を身近な例から解説した書。巻末に参考文献。<理論言語学がスッパリ解決できるようなことは多くない。しかし理論言語学の知見には、「言いたいことがうまく言えない」とか「思うように伝わらない」、「相手の意図が分からない」などと言った漠然とした問題に対して、見通しをクリアにするヒントが多数隠されている>と。⇒2025/03/20
tamami
51
本書を中程まで読みながら、強い既読観に囚われ積ん読本の書棚を探したりもした。一年ほど前に読んだ同著者の新書本『ヒトの言葉機械の言葉』に引用された例文に似たものを感じたのかも知れない。理論言語学が専門という著者は、我々がふだん読み書きする文章や会話を取り上げ、誤解を招くような話し方や書き方の例を具体的に指摘し、修正あるいは代替案を示してくれる。誤解のもとは、言葉のもつ多義性や複雑な文章構成にもあるとする説明は分かりやすい。一人で文章を推敲したり、他人の書き物を点検する際の参考書として大いに活用が期待される。2021/12/29
-
- 洋書
- Nerdcrush
-
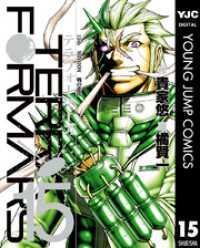
- 電子書籍
- テラフォーマーズ 15 ヤングジャンプ…