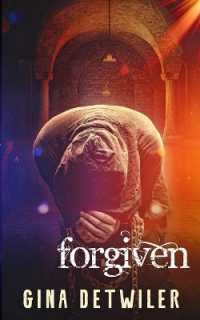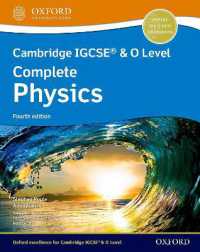内容説明
信長の独創力、家康の不動心、信玄のカリスマ性…若き武将に、儒学を基にした行動哲学と深い教養を授け、君主論や軍学を教え、闊達で逞しい人生観を確立させた臨済宗の僧侶たち。自らも軍師、諜報役、易者、医役を務め、武将のブレーンとして、政治顧問や公家との交流から合戦の勝敗まで左右した禅僧たちの実像から、名将と禅宗との秘史に迫る斬新な論考。
目次
第1章 武将にとって禅とは何だったか
第2章 子弟の教育機関だった禅寺
第3章 武将幼少時の師となった禅僧
第4章 戦国の合戦と禅僧
第5章 易者でもあった禅僧
第6章 信長「天下布武」の陰に二人の禅僧
第7章 政治顧問に迎えられた禅僧
著者等紹介
小和田哲男[オワダテツオ]
1944年静岡県生まれ。早稲田大学大学院文学研究科博士課程修了。文学博士。静岡大学教育学部教授。日本中世史研究の第一人者(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
とし
10
戦国時代、多くの僧が戦国大名たちの政治・外交面におけるブレーンとなっていた。なかでも臨済宗・五山系の禅僧は、栃木の足利学校で外典を学び、外交、学問、占いといった分野で大いに活躍している。現代の僧とはイメージが違う、当時の禅僧のイメージを描くことにはある程度成功してると思う。雪斎とか崇伝とか沢彦とか、本当に有名どころの僧が紹介されてるんだが、個人的にはもっと多くの大名について具体例を知りたかったかなあ。まあ、この文章量なら仕方ないか。2016/06/10
maito/まいと
4
戦国時代、領土拡大だけでは国を治められなかった時代。学問や知識、そして思想や理念で様々な人たちをまとめていった者たち、その誕生に貢献した僧たちにスポットを当てた一冊。信長の焼き討ちや武装化などが思い浮かんでしまう当時のお坊さんだが、一級の寺院では、修行と研鑽の中で生まれた当時のインテリ集団が、少なからず存在していた事実は、おもしろい観点。言われてみれば上杉謙信、伊達政宗など、禅僧に幼少時代教わってきた武将エピソードは耳にしたことがあったなあ。戦国武将の成立の裏側、興味ある方はご一読を~2012/08/23
Go Extreme
1
武将と禅の関係:臨済宗 君子論 忠孝 無為 文芸 五山文学 香語 法要 禅宗影響 禅僧指導 禅修行 精神的修養と戦略:無心 自己省察 坐禅 瞑想 冷静さ 判断力 忍耐力 リーダーシップ 精神安定 内面的成長 精神集中 教育と文化:禅寺教育 書道 詩 茶道 礼儀作法 中国古典 教養 育成 武道 読書 教化 政治と助言:政治顧問 易経 軍師 天下布武 調停 和解 支援 統治助言 占い 助言影響 政策指導 具体的事例:今川義元 上杉謙信 徳川家康 直江兼続 織田信長 武田信玄 策彦周良 沢彦宗恩 玉堂宗条 雪斎2025/03/25
マサトク
1
戦国大名と禅僧との関わりを様々な角度から描く。右筆としての侍僧もいれば軍師としての僧侶もいたし、終章の信長との関わりは意外でもあった。情報量も多く、読み返しながら寺を回りたい感じだなあ。足利学校が学校というより(易占も学ぶような)禅堂であったというのは面白い。図書館で借りた本だけど、手元においておくべきかも。2019/09/10
rbyawa
1
g126、全体的に面白い内容ではあったものの、エピソー集と言ったところで結論としては若干物足りなかったかな。足利学校は定期的に話に出てくるので知ってはいるし、そこが事実上の禅宗の学校になっていたのは説明されたらわかったものの、なぜそうなったのかがよくわからないし、その卒業生であることが大名に仕官に有利となる経緯もわかりにくかったように思う、書いてあることは全く疑ってはいないのだけれどね、禅宗に対しての権力者の後押しのようなものがあったという説明が欲しかったなぁ。どこかの家が始めたというのもありそうだけど。2016/12/17