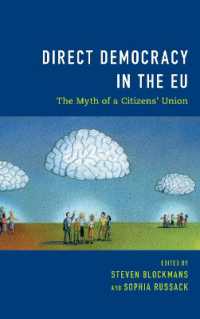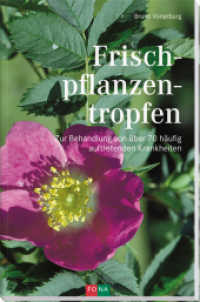出版社内容情報
絵筆をとれば文人画から俳画まで自在にこなし、俳句を詠んでは芭蕉とならび、書をよくする。彼こそ江戸ルネサンス最大の総合芸術化=文人だった!
内容説明
絵筆をとれば文人画から俳画まで自在にこなし、俳句を詠んでは芭蕉とならび、書にも抜群のセンスを示す蕪村こそは画壇・俳壇を股にかけた江戸ルネサンス最大のマルチアーティストだった!旅を重ねた若き日から、京都に腰を落ち着けた円熟の晩年まで、大胆に変貌しつづけた蕪村の世界を丹念に追う。
目次
第1章 蕪村 江戸の総合芸術家(蕪村、二十の旅立ち;修業時代;総合芸術の完成期)
第2章 俳人蕪村の実力
附 蕪村句のイメージを求めて
著者等紹介
佐々木丞平[ササキジョウヘイ]
1941年、兵庫県生れ。65年、京都大学文学部哲学科卒業。同大学院文学研究科美学美術史学専攻博士課程修了。日本近世絵画史専攻。京都府教育委員会、文化庁、京都大学教授をへて、2005年、京都国立博物館館長に就任
佐々木正子[ササキマサコ]
1950年、神奈川県生れ。76年、東京芸術大学美術学部絵画科卒業。日本画家、京都嵯峨芸術大学教授。99年、夫・丞平とともに、円山応挙の研究で日本学士院賞受賞(夫婦での受賞は同賞の創設以来初めて)
小林恭二[コバヤシキョウジ]
1957年、兵庫県生まれ。81年、東京大学文学部美学科卒業。84年、「電話男」で第3回「海燕」新人賞受賞。98年、『カブキの日』(98講談社)で第11回三島由紀夫賞受賞
野中昭夫[ノナカアキオ]
1934年、新潟県生れ。57年、早稲田大学商学部卒業後、新潮社写真部に入社。「芸術新潮」のスタッフ・カメラマンとして長年、活躍。連載「ローカルガイド」及び「現代人の伊勢神宮」で日本雑誌写真記者会賞受賞。現在、フリー(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mocha
sofia
しーもあ
Mマジパン
Fumi Kawahara
-
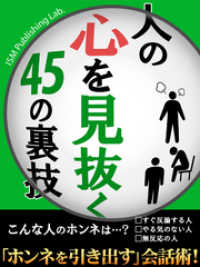
- 電子書籍
- 人の心を見抜く45の裏技 ISMPub…