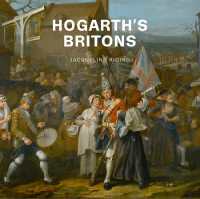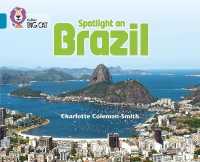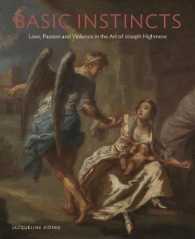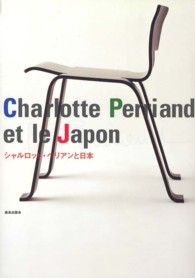内容説明
1859年に来日、攘夷の嵐が吹きすさぶなかで、何よりもまず言葉の架橋をと、和英辞書を編纂、聖書の日本語訳に精魂を傾けたアメリカ人宣教医。その多難の道を、激動の時代を背景に辿る。
目次
1 維新前夜の日本へ(「生麦事件」を診た人;モリソン号事件と日本開国)
2 洋医ヘボン(日本人教師ヤゴロウ;ヘボン以前の日本語研究)
3 攘夷の時代(帝と大君;大村益次郎ら入門;ヘボン夫人の塾;横浜アカデミー;薩英戦争と下関事変;谷戸橋畔39番;岸田吟香)
4 和英語林集成を読む(ヘボン辞書の特色;カナ遣いと漢字;普通辞書としての工夫;言葉の変遷とヘボン式ローマ字)
5 聖書を日本語に
6 長すぎた旅
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
の
2
医学・言語・宗教が変わりつつあった時代。2021/12/13
エディン
1
ヘボンと言えばヘボン式のローマ字で有名ですが、彼は、江戸時代の末期、医者として、宣教師として日本にやって来ました。キリスト教禁制の中、「和英語林集成」という辞書を作り、聖書の翻訳をしていくエネルギーと苦労は想像を絶するものがあります。彼が日本に残した足跡は医学、教育、キリスト教の世界で後の多くの人に受け継がれていますが、ヘボン自身は、33年過ごした日本を去り、米国に帰って寂しい晩年を迎えたようです。2011/03/27
Kumo
0
辞書編纂者としてのヘボンは耳にしていたが、その人となりについては全く知らなかった。それだけに冒頭の生麦事件譚は印象的。激動の時代、政治も社会も思想も、また日本語も大きく変遷する時代を、一人のアメリカ人の生涯を通じて感じる。2015/09/15
pikamura
0
堅苦しい見た目と題名から驚きの面白さ。辞書編纂と聖書翻訳にかけるヘボンの思い、英語と日本語の出会い、幕末から明治の世情を生き生きと描いて美しい。2018/11/15