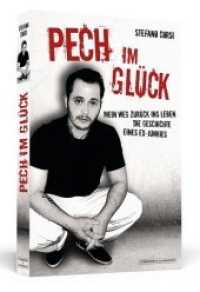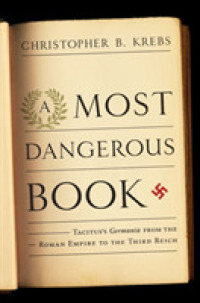内容説明
1616年夏、北極海。イングランドの捕鯨船が帰国の途に着こうとしていた。トマス・ケイヴという名の寡黙な男を一人残して―。明けない夜。うなりをあげる吹雪。闇を染めるオーロラ。雪と氷に閉ざされた極限状態のなか、ケイヴは、日々のできごとを克明に記し、生きるために獣を狩り、思い出深いヴァイオリンをアザラシたちにむけて奏でる。ケイヴはなぜ、極北の地に残ったのか。底知れない哀しみを抱えた男の越冬と魂の救済を重ねあわせた、胸をゆすぶる物語。英国人女性作家が400年前の航海日誌と豊かなイマジネーションで紡ぎだした、壮大なスケールのデビュー長篇。
著者等紹介
ハーディング,ジョージーナ[ハーディング,ジョージーナ][Harding,Georgina]
1955年英国生まれ。ロンドンの出版界で働き、80年に来日。翌年まで東京で編集の仕事に従事。以後アジア各地、ヨーロッパ大陸を旅してまわる。現在はエセックス州コールチェスター在住(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
どんぐり
104
現在のノルウェー領スヴァールバル諸島にある島。イングランドの捕鯨基地が置かれたのが1611年。この捕鯨事業が始まった頃、船乗りたちと賭けをした一人の男が、たった一人で冬を過ごした話である。男が無謀な行為をしたのには、理由がある。船乗りが家に戻っても、再会する妻子を喪っていたからである。寒さと途切れることのない闇の極夜、死を招く無為、無気力、怠惰に抗いながら男が見たのは、自分の心の声にこたえる心のなかの像。シロクマやトナカイを狩猟するサバイバル要素もあるが、冒険物語と違って霊的な部分が後半になって強くなる。2022/01/05
藤月はな(灯れ松明の火)
84
17世紀、賭けでたった、一人、北極で一年、過ごすことになったトマス・ケイヴ。容赦無い自然の中、食糧を調達し、病に臥し、アザラシにバイオリンを弾きながら、幻想と会話して無常と向き合う。異色でいて日常とも言える穏やかな生活の方が彼にとっては恩寵だったのだろう。そう思うと喪った者達の悲しみに打ちひしがれていた彼の魂は彼の地に取り残されてしまったのかもしれない。その後の孤独を引き連れてイングランドを放浪する彼はまるでラザロのよう。2016/09/05
kasim
36
1616年、まだ南蛮屏風みたいな服装をしていた時代に、捕鯨船の乗組員が北極で一人越冬する。麻痺するような寒さと闇のなか、失った家族の幻がさりげなく訪れる日々は美しく喚起される。平凡で堅実な人生を送るはずだった彼はなぜ自分の意思で残ったのか。一方で後日談の部分はもう少し膨らみが欲しかったところ。若い船員の語りももう一工夫ほしい。アイディアよし、描写よし、人物造形よし、洞察よし。もう一声。難しいものだな。2021/01/20
Apple
25
トマス・ケイヴが極北に残って冬を越すことを選んだ理由が、彼自身の過去に由来していることが判明してくるストーリーの流れが印象的でした。極限状態に身を置く中で、自分の、あるいは人間の罪と向き合い、洗い流していくかのような生活だと感じました。極北の冬を越え陽が出た場面が、太陽がいかに生命の象徴であるかを感じられて良かったです。また、語り手の1人である少年のトマス・グッドラードとの友情がまたよかったように思います。サバイバル物の話としても充実していて、なかなか素晴らしい作品だと思いました。2025/09/13
キクチカ いいわけなんぞ、ござんせん
23
北極圏で1人で一年を過ごした捕鯨船員の男の話。賭けに乗ってそのような事になるのだが、寒さと真っ暗な極夜で向かい合う過去。必要なだけ自然から分けてもらう、という気持ちがなく貪欲に鯨やアザラシの殺戮を繰り返す人間のさもしい心も、ひとりぼっちの生活で見えてくる。人間の欲望には限りがない、という事も恐れる。 それにしてもこの時代のお産は命懸けで大変だなあ。2023/06/12
-

- 和書
- アメリカ・キリスト教入門