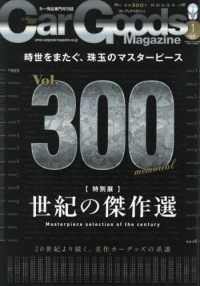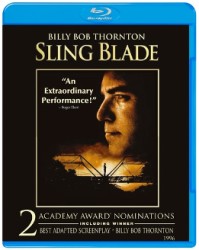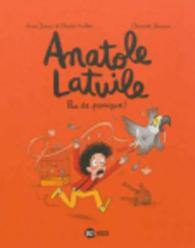- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 哲学・思想
- > 構造主義・ポスト構造主義
出版社内容情報
人間の性と欲望に関する概念は歴史的にどう形作られてきたのか。現代思想の泰斗の遺稿を編集した最終巻、没後三十余年でついに刊行。
内容説明
人はどのようにして「欲望の主体」となったか。没後三十余年現代思想の巨人最後の主著ついに完結!2~5世紀のキリスト教教父の文献を丹念に分析し、悔悛の実践、修道制の発達、処女・童貞性と結婚など、現代に連なる「欲望の解釈学」の形成を解明する。
目次
第1章 新たな経験の形成(“天地創造”、子づくり;労苦を要する洗礼;第二の悔い改め;技法中の技法)
第2章 処女・童貞であること(処女・童貞性と節欲;処女・童貞性の技法;処女・童貞性と自己認識)
第3章 結婚していること(夫婦の義務;結婚の善、その複数の善;性のリビドー化)
著者等紹介
フーコー,ミシェル[フーコー,ミシェル] [Foucault,Michel]
1926‐1984。20世紀のフランスを代表する哲学者。1960年代からその突然の死にいたるまで、実存主義後の現代思想を領導しつづけた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
燃えつきた棒
35
ここまで、ナメクジが這うように膨大な時間をかけて、断続的に『性の歴史』全四巻を読んできたが、残念ながら僕にはフーコーが何を言いたいのかピンと来なかった。というか、はっきり言ってつまらなかった。 ということで、以下の感想はほとんどの人にとって何の参考にもならないだろう。/ フーコーが何を言いたいのか分かっていないのだから、批判などできようはずもないが、それでも若干の不満が心に残った。 フーコーは、本書で「欲望の解釈学」を展開するにあたって、2〜5世紀のキリスト教教父たちの文献を分析しているが、それは→2025/06/14
roughfractus02
7
知の言説から2つの規範(他者の内面化した道徳と自己への配慮)における権力へという前3巻の探究後、著者の死は草稿を収めた本巻を残した。自己への配慮がキリスト教的な他者規範の反省機構を強いる生権力から逃れる「新たな経験」に着目する著者は、自己への配慮の技法を純潔(童貞と処女)を修練と捉えたローマ期の文献を検討する。この「新しい経験」では、結婚は無意志とされる性的リビドーを他者への欲望と捉えて意志と対立させ、性を生殖の管理とはしない。婚姻者同士の意志の中の無意志として自己との関係に置く技法の契機とするのである。2024/12/01
いたま
2
長らく未刊かつ未完の著作であった『性の歴史』の最終巻(とはいえ、遺稿の再編集なので著者の意図するものではないだろう)。第4巻に入り、全巻から着手していた古代世界の性倫理が、どのように初期のキリスト教に受け継がれ、発展していったかが丹念に説明される。大方の性的な禁止事項や規範はどの文化にもあるが、キリスト教の倫理がいかに夫婦を中心とする性を合理化し、近代の厳格な性規範につながるものを用意していったのかが明かされる。性に関する知識/技術の構築があったということでフーコーらしい筆致。遺稿とはいえ完結した著作。2023/10/30
ロータス
2
Ⅲまでを高校時代に読んでいたので完訳となったこちらを手に取ったが、翻訳者が違うためか非常に読みやすかった。/キリスト教以前に異教であるストア派に厳格な禁欲主義が発生し、それがキリスト教の教義に影響を与えたというのは興味深い。たしかにクレメンスを筆頭に聖書より厳しい禁止事項を掲げている。しかし結婚より童貞や処女を礼賛し、子づくりを目的としない性行為を不浄とする思想は理解しがたい。神への形式的懺悔(告白)、良心の自己監視システムによる苦行、等、それらが救いへの道だとしても、私にはそんな生き方は無価値に思える。2021/02/24
takao
0
ふむ2025/06/23
-

- 電子書籍
- 【フルカラー】闇の王、たかがメイドを偏…
-

- 電子書籍
- 最強ジャンプ 2022年6月号