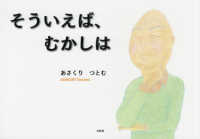出版社内容情報
燦めきと謎に充ちた二十一世紀の「夭逝の画家」。その生涯を辿り、画業に迫る。高校二年の夏、中園は突如「絵が描きたい」と美大予備校に通い始める。東京藝大に進み、「今年は天才がいるよ」と在学時より注目され、卒業の翌年には著名ギャラリーで個展を開催。将来を嘱望されながら二〇一五年、二十五歳で急逝……両親、友人、恋人たちへの丹念な取材と書き残された百五十冊ものノートなどから読み解く本格評伝。
内容説明
高校2年、16歳の夏、バスケに熱中していた中園は突如、「絵が描きたい」と訴え、自室の壁に描き始めた。藝大を卒業した翌年の2013年には小山登美夫ギャラリーで初の個展を開催。周囲をハラハラさせつつも、魅了してやまず夜の森を彷徨い歩く、天使みたいな若者だった。両親、友人、恋人たちなど、あらゆる関係者への取材と書き残された150冊ものノートから読み解く本格評伝。
目次
はじめに わからなさの手触り
第1章 ホラー映画観たい、みたいな気持ち
第2章 絵のマグマ
第3章 忘我の季節
第4章 薄い透明な膜
第5章 どうにもできないこと
第6章 絵と音楽の出来る場所
第7章 消えない光
著者等紹介
村岡俊也[ムラオカトシヤ]
1978年生まれ。鎌倉市出身。ノンフィクション・ライター(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
どんぐり
80
25歳の若さで亡くなった夭折の画家・中園孔二の評伝。初出は『芸術新潮』の連載。中園孔二が遺した作品は、高校時代からの9年間で約600点、一部の作品は東京都現代美術館に所蔵されている。藝大の学生時代から天才といわれ、「中園が駆り立てられるように絵を描いているのが羨ましかった。藝大生のほとんどは、絵を描いているってことが自分のアイデンティティになっているのに、何を描けばいいのかわからない。それでも絵を続けるしかない。だから苦しむんです。でも中園は、描かざるを得ないから描いている」という証言がある。→2025/01/07
kaoru
72
夭折した天才画家・中園孔二の生涯を友人が綴った評伝。バスケに熱中する高校生が不意に絵を描くことに目覚め、藝大で天分を開花させる。誰にでも好かれながら「生と死のギリギリの辺りを歩いていた」彼は野宿したり電車のトンネルにはいったりという行為を続けながら爆発的に創作に打ち込んだ。音楽を愛し思索をノートに綴った彼の言葉に打たれる。「絵は、自分自身の片方である」「絵画は性質的に、うそのつくことのできない、純度の高い”優しさ”である」彼の絵はときに不穏であり、生きることへの不安や哀しみが現れているように感じられる。2024/01/09
kawa
28
2015年、25歳で事故死した早熟の画家・中園孔二さんの評伝。短期間に550点以上もの作品を残したと言う。本書にも12点の作品が口絵紹介される。「ダイレクトに伝(わ)ってこない美術はすきじゃない コンセプトや美術的教養のようなものをふまえた上でしか理解できない美術って、ぼくの中ではなんか違う。」と言う中園氏。残念ながら感性鈍い私は、本書を読んで作品にさらに親近感。補助輪付き自転車で20キロ彼方のランド・タワーに一人でいってしまったという氏。天才となる人間の衝動は幼くても異次元ということだろうか。2024/02/23
チェアー
7
印象に残ったのは筆者の誠実さだ。決して自分を消しているわけではない。自分の出し方がまっとうで違和感がないのだ。関係者にじっと話を聞き、自分の中に取り込み、わからないことを分からないまま残しておく。これが本来のあるべき書き手なのだと感じた。 「いま」が永遠に続く。それを常に通過し続ける私が見る。それは羨ましくもあり、残酷なことだ。 2023/10/09
伏木
6
NHKの番組で中園を知った。久しぶりにどきどきした。 昔は現代美術をよく見に行った。 近代の造形表現は単に表面の問題と考えるのが主流だった。 支持体と表面。 小学生のころ、「何年生?」と聞かれるのが不思議だった。 「見ればわかるだろ」と思っていた。今は全くわからない。 画家は私たちの見えないものを見ている。 今この時代に、こんな天使のような純粋な人がいたのだ、これは誇張でも何でもない、人の言葉が伝えているのではない、事実がそれを証明している。2024/05/28