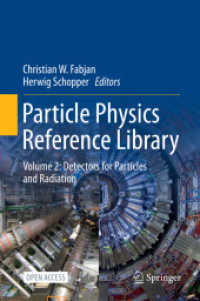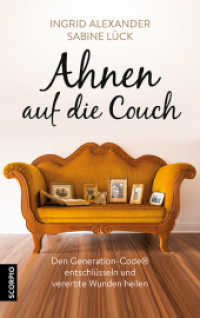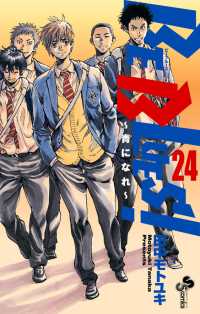内容説明
東京都日本橋区にある老舗の跡取り息子。彼は、中学進学を控えた国民学校六年生の夏、山奥の寒村の寺に学童疎開することになった。閉鎖生活での級友との軋轢、横暴な教師、飢え、東京への望郷の念、友人の死、そして大空襲による実家の消失、雪国への再疎開…。敗戦前後に多感な少年期を過ごした小林信彦が、戦後六十年の“現在”だからこそ書かなければならなかった、「波」好評連載の話題作。
目次
眠ったような街
第一の異界
飢餓への序曲
からくり
赤蛙
生きつづけること
東京の光
空襲始まる
真紅の球体
昭和二十年三月十日
大空襲のあとで
第二の異界
山鳩の声
その前夜
昭和二十年八月十五日
日盛り
アメリカ兵の〈過剰な〉親切
ヒロポン
望郷
雪の中
東京への道
帰郷の方法
〈転入〉の法則
歳末まで
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
79
2005年発行。著者の少年時代、身の回りのことや、集団疎開先での出来事、友達の死、敵の戦闘機から機銃掃射を受け死に直面したこと、やがて終戦。現代社会で疎開という言葉自体わからないものであり、実際に体験して記憶に残っている方は皆さん90歳は超えているだろう。食糧不足や栄養用失調で同じ境遇にならないことを肝に銘じて子孫に伝えていく必要があると思った。図書館本2024/09/27
sivad_smiles
5
作者がモデルなんでしょうね、戦時中の疎開って2種類あったとは知らずです。今よりずーーーーーっと距離感のあった東京と新潟の感覚値は新鮮に感じつつも「都会っ子」に対するいじめはあった訳ですねぇ。 2012/10/26
yuzuriha satoshi
3
「エンコかシュウダンか」主人公が判断を迫られる場面から始まる これは縁故疎開か集団疎開かという意味 「東京少年」が余儀なくされる集団疎開先 埼玉・名栗村でのこどもたちの残酷で陰湿な集団生活 縁故疎開先の新潟・新井での過酷な冬越し 東京・両国へ戻るまでの三年九ヶ月を戦中の風物を織り込んで描いた 両国叙情詩三部作の第一部2011/10/14
コウジ
2
戦中の空気や迫りくる空襲の恐れ、日本指導層や大人への不信などを書くながら、のちの小林信彦らしい映画や芝居への興味もあり、ぐいぐい読めた。ずっと「本音で申せば」を愛読していた私にとっては語り口にも慣れていたせいか興味深く読めた。ただ東京のプライド田舎への軽蔑だけは・・・2018/08/12
horuso
2
東京で生まれ東京で育った少年が、集団疎開と縁故疎開を経て、東京に戻る物語で、文学的価値を否定はしないが、それよりも、その時代を生きた人の証言として貴重だと思う。それにしても、ラストでとうとう、都の中の都=日本橋に帰り着いて充足感に満たされる主人公に、冷ややかな気持ちを感じざるを得ない。主人公が、大晦日の東京を伝えるラジオに対して、『(莫迦野郎……)とぼくは思った。ぼくがそれらの人波と関係のない、雪の中にいるからであった。』と感じたのと同じだ。こちらはいま東京にいないんだから!2015/05/15