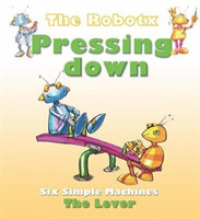出版社内容情報
「勉強しなさい」と言っても
どんなに危険だと教えても、聞かない
そんな10代は0歳-3歳期に次ぐ第2の脳の成長期
この時期にこそ、子どもは伸びる!
最新の脳研究が明かす意外な真実
子どもの脳の発達やその後の人生に重要で永続的な影響を与えるのは、ごく幼い時の経験(一般に「0歳から3歳まで」と言われる)という話は、よく耳にするだろう。これは
まさにそのとおりである。だが青少年期も、脳の柔軟性が高まる第2の時期だということはほとんど知られていない。――(略)――青少年期は、私たち大人が影響を与えてやれる最後で最良のチャンスなのである。―本文よりー
【著者紹介】
米テンプル大学の発達心理学を専門とする教授。米国にて思春期・青少年期の発達心理学研究を40年に渡って続けてきた。米国心理学会発達心理学部門のトップを務めた経験もあり、この分野における権威。
内容説明
青少年は、1人よりも友だちと一緒にゲームをした時の方がより危険を冒そうとする。黄信号を頻繁に無視し、事故も多くなる。肝心なのは、仲間というものが青少年期の脳に、大人の脳とは違う影響を与えることである。親は、青少年が集団でいると、1人の時よりまずい判断をすると知っている必要がある
目次
第1章 3歳と15歳、どちらの脳が柔軟か?
第2章 記憶が強烈に残る若者の脳
第3章 史上最長になった青少年期
第4章 10代の判断力とは?
第5章 子どもを子ども自身から守るには?
第6章 最も重要なのは自己制御力
第7章 親にできること
第8章 高等学校を考え直す
第9章 裕福な子どもの脳と貧乏な子どもの脳
第10章 10代の犯罪と脳
著者等紹介
スタインバーグ,ローレンス[スタインバーグ,ローレンス] [Steinberg,Laurence]
米テンプル大学の発達心理学を専門とする教授。米国にて思春期・青少年期の発達心理学研究を40年に渡って続けてきた。米国心理学会発達心理学部門のトップを務めた経験もあり、この分野における権威
阿部寿美代[アベスミヨ]
1964年生まれ。英・仏・独語翻訳家。早稲田大学およびフランス・リヨン第二大学卒業。1987年より、NHK記者として科学、医療、教育などを担当。報道局国際部を経て、96年退職。98年に『ゆりかごの死~乳幼児突然死症候群(SIDS)の光と影』(新潮社)で、第29回大宅壮一ノンフィクション賞受賞
宝槻泰伸[ホウツキヤスノブ]
小学生から高校生までを対象として学習塾「探究学舎」(東京・三鷹市)代表。高校を退学。大検を取得し、独学で京都大学に進学する。大学卒業後は高校や職業訓練校で教壇に立つなどした後、生徒の自発性と探究心を育てる教育を目指して探究学舎を開校(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さとう
おだまん
Humbaba
KTakahashi