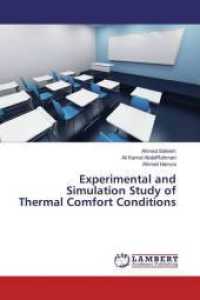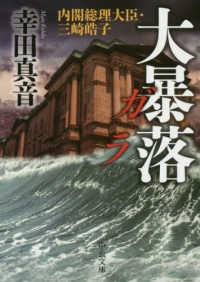内容説明
伊勢物語の「むかし、をとこ有けり」の一句にこめられた意味とは?芭蕉の俳号・桃青に秘められた壮大な望みは何か?能は生の意味を死の側から照らすのに対して、歌舞伎や人形浄瑠璃は死を生の側から見つめるドラマだ。古典の面白さを優しく語るエッセイ集。
目次
前書きに代えて
詠むと読むと
「源氏物語」現在形
二人のスター
漢詩への感謝
おででこめがね
平生則辞世
著者等紹介
高橋睦郎[タカハシムツオ]
1937年、北九州八幡市生まれ。福岡教育大学教育学部国語国文科卒。62年に上京し、現代詩、俳句、短歌、新作能、オペラなど多彩な分野で創作活動を続ける。82年『王国の構造』で藤村記念歴程賞、87年『王女メディア』で山本健吉選山本健吉賞、88年『稽古飲食』で読売文学賞、同年『兎の庭』で高見順賞、93年『旅の絵』で現代詩花椿賞、96年『姉の島』で詩歌文学館賞、2007年織部賞、10年『永遠まで』で現代詩人賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Mijas
38
著者の講演をまとめた本。古典への思い、詩歌を日本語で声に出して読む大切さが述べられている。話題は、源氏物語から和歌、漢詩、歌舞伎に及ぶ。日本の詩歌は「間」から生まれる情緒を重視してきたこと。それが国民の感受性を豊かに深くした。日本人は、無名の国民の誰もが潜在的に辞世の詩歌の作者であるという民族だが、中国文学からの影響であるという視点。数多の政変で犠牲になった政治家は同時に詩人であり臨刑詩を残した。それが万葉集の挽歌となる。卓越した資質であった大津皇子の辞世の漢詩に日本的な繊細さをみる。(「漢詩への感謝」)2017/12/07
toki12
0
ギリシア悲劇と能が似ているp202若者は学校でよりはるかに多く酒場と旅で学ぶ p2202012/09/18
-
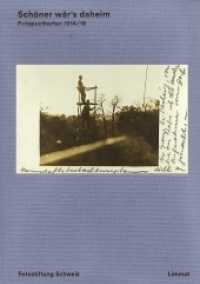
- 洋書
- Schöner wä…