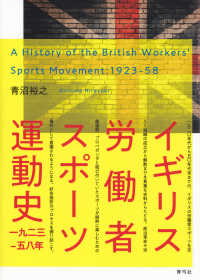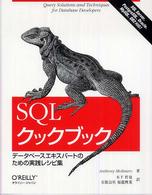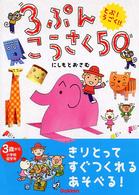出版社内容情報
『張込み』で出会い、『砂の器』を生んだ男たちが幻の作品『黒地の絵』で別れるまで――。松本清張の映画化に挑んだ昭和の熱い日々。
内容説明
10日で終わるはずだった『張込み』佐賀ロケ。だが彼らは1ヵ月以上たっても帰ってこなかった。やがて男たちは『砂の器』を生み、幻の映画『黒地の絵』に立ち向かう…。松本清張作品の映画化に挑み続けた昭和の熱い日々!
目次
第1部 ドキュメント『張込み』(クランク・インまで;役者たちの事情;佐賀入り;山を求めて)
第2部 『砂の器』、そして『黒地の絵』(清張ブーム到来;それぞれの旅立ち;清張の企て)
著者等紹介
西村雄一郎[ニシムラユウイチロウ]
ノンフィクション作家、映画・音楽評論家。1951年、佐賀市生まれ。早稲田大学第一文学部演劇科を卒業後、「キネマ旬報」パリ駐在員。帰国後、映像ディレクターとしてビデオCM、ビデオクリップを演出。1985年から古湯映画祭(佐賀市富士町)の総合ディレクターを務め、その功績により90年に「佐賀新聞文化奨励賞」受賞。2001年公開映画『いのちの海』(原作・帚木蓬生)で脚本を初執筆(石堂淑朗と共作)。03年にオープンした「映像ミュージアム」(埼玉県川口市)の総合監修を担当(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
86
初めての清張映画は『砂の器』だったが、感動して原作を読んだら全く面白くなくて唖然とした。その後『張込み』をビデオで見たが、汗まみれな刑事の姿に息詰まるほどの暑苦しさを感じた。この2作の製作現場を伝える本書は『張込み』撮影部隊の拠点となった旅館でスタッフにかわいがられた著者だけに、日本人が映画に夢中だった時代の熱気を今に伝える。後半、清張が『黒地の絵』映画化に執心し霧プロを設けながら、困難さを自覚し消極的になった野村監督と対立し空中分解するプロセスは生々しい。製作を強行していたらどうなったか想像できないが。2022/01/15
遊々亭おさる
17
映画が娯楽の王様であり、推理小説が文学の異端として軽視されていた時代に制作された一本のミステリ映画に賭けた野村芳太郎の情熱を切り取った前半と、一本の映画制作をめぐり袂を分けた二人の才人の物語を描く終章、一粒で二度美味しいグリコのような一冊。会社に従順でいるだけでは良き仕事にはならない教訓と共に、映画黄金時代の地方都市の世相を覗き見ながら松本清張が生涯映画化を望みながらも果たせなかった『黒地の絵』に関する逸話に清張作品に通低する影のテーマに思いを巡らせる…。映画好きでありミステリ好きな人にとっては良書かと。2016/01/02
ぐうぐう
13
なんとももどかしい一冊。タイトルにあるように、清張映画に関わった人々の熱い想いを映画『張込み』製作を柱に描いていこうとするのだが、読み終わって感じるのは、ラストの章で紹介される、果たされなかった『黒地の絵』映画化のエピソードのほうがよっぽど興味深く、そちらを柱にしたほうがこの主題をより強烈に伝えることができたのではないか、という疑問だ。著者がそれをしなかった(もしくはできなかった)のは、映画『張込み』のロケ隊が宿泊したのが著者の実家である旅館であったという事実だ。(つづく)2015/08/16
keroppi
5
著者の実家が「張込み」のロケ旅館だったことから、その当時の事が詳細に綴られていく。野村芳太郎、橋本忍、山田洋二、宮口精二、黒澤明、等々、それぞれの思いが絡み合いながら、映画が生まれ、また、消えていった。著者の個人的思い入れの強い本ではあるが、それだからこそ、他の評論では見られない訴えかけるものがある。2015/08/01
のぶ
4
某雑誌の書評を読んで購入した本。第1部は1958年の「張込み」の裏話。 第2部は脚本家橋本忍や山田洋次の駆け出し時代の話や映画化されなかった 「黒地の絵」の話。内容は悪くない。が、これらの事を今知っている人が どれだけいるだろうか?営業的には厳しかったと思うが、これを否定すると すぐれたノンフィクションが世に出なくなる。大手出版社の英断を評価したい。 個人的に「張込み」はビデオで観ており、橋本忍の著作も読んでいたので、 楽しめた。邦画好きの人にはお勧めの一冊。2015/05/10