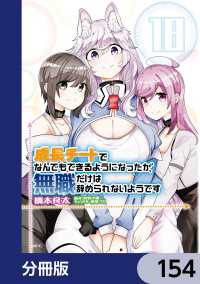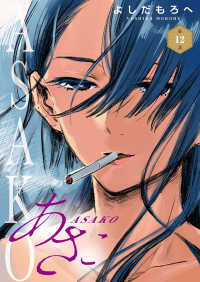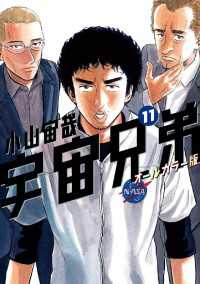内容説明
樹齢千年の檜は、大工の技と知恵で、建物になっても千年は持ちますのや―。木を知悉する「最後の宮大工棟梁」が、職人の技術と魂について語り尽くした。
目次
宮大工という仕事
木を長く生かす
木の二つの命
礎石の大切さ
木の触り心地
飛鳥の工人に学ぶ
古い材は宝もの
千年の命の木を育てる
宮大工棟梁の自然観
道具と大工の魂〔ほか〕
著者等紹介
西岡常一[ニシオカツネカズ]
1908年奈良県生れ。法隆寺金堂、法輪寺三重塔、薬師寺金堂、同西塔など、檜の巨木を使って堂塔の復興を果たした最後の宮大工棟梁。文化財保存技術保持者、文化功労者
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。