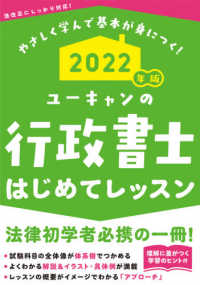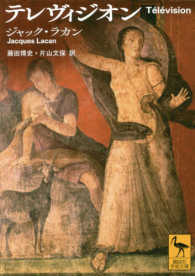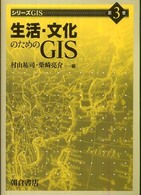内容説明
凋落しつつある資産階級に生まれ、母の死後、モスクワの親戚宅に引き取られたユーリィ・ジバゴは医者を志していた。一方、ロシヤに帰化したフランス人の娘ラーラは母の愛人との泥沼の関係を断ち切り、新しい生活を築こうとしていた。やがて人人に第一次世界大戦とロシヤ革命の波が襲いかかる―。動乱の時代を背景に波瀾の運命が待ち受けるジバゴとラーラの青春を描く。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
391
上巻では随分たくさんの人物たちが登場するし、場面もまた甚だしく入れ替わる。後半あたりからは、ようやくタイトル・ロールを背負うジバゴが主人公らしくなってくるが、それにしてもメイン・プロットも未だはっきりとした像を結ばないし、展開の行く末も予想がつかない。なんだか、混沌とした薄明の中をさまよっているような感がなくもない。そして、彼らの行動と共に、連鎖的に生起してゆくロシア革命が同時に進行してゆくのである。これは今後もより深く物語に関与してゆく、あるいは物語そのものを支配してゆくものと思われる。2021/05/13
のっち♬
143
第一次世界大戦とロシヤ革命の動乱時代を生きるジバゴとラーラの波瀾と苦難に満ちた軌跡。世相と生活の変化のディディール追求は仔細で、ジバゴを主軸化しても個と全体双方が主役かつ背景のような感覚。この独特のバランスが歴史のダイナミズムや個の頑強と無力を表出させ、凝らされたシンボリカが一見素朴な散文に慎ましく詩性を添えている、こちらも主客転倒が柔軟。上巻で印象的なのはジバゴがアンナに語る独自の死生観。「他者の中にある人間、それこそが人間の本質、魂なんです」—ここに激動の時代の中に『永遠の記憶』を求める著者を感じる。2023/01/08
NAO
78
没落した名家とはいえ医者として食べる者には困ってはいないジバゴ。母が裕福な弁護士の妾で自分もその弁護士の愛人にさせられてしまったラーラ。何度かの出会いを繰り返す二人、彼らの生活の合間から垣間見える革命期の動乱とその奥に潜む闇。2019/03/15
k5
62
モスクワに住んでいるときに、チュルパン・ハマートヴァがラーラ役でドラマをやっていて、DVDを購入して勇んで観たわけですが、私のロシア語力では筋が追えなくなり、小説を読み返してから観よう、と思ってはや数年。やっと小説を手に取りましたが、これ、むつかしいなあ。メロドラマとしてみると、どこか既視感がある話ばかりですし、ドストエフスキーみたいに説明ゼリフで哲学をぶつけあう感じでもない。訳者の江川卓さんの解説にあるように、シンボリズムの文脈から丹念に読む必要がありそう。要再読かなあ。2020/07/04
みっぴー
60
1900年初期のロシアが舞台です。日露戦争に続き、第一次世界大戦、、、。もはや帝政の瓦解は火を見るより明らか。怒れる市民が立ち上がり、革命の波が押し寄せる…。帝政から社会主義国家へ生まれ変わろうとするロシア。そこに生きる人間達のドラマを描いた作品です。長い人名、地名、複雑に絡み合う人間関係、膨大な情報量に泣かされ、何度も何度も挫折しかけました。江川訳でなかったらとっくに投げ出していたと思います。くたくたになりながら、下巻へ。2016/05/23