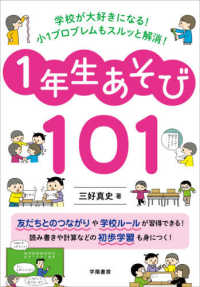内容説明
食べること、歩くこと、泣けること…重い病に侵され、日常生活のささやかながら、大切なことさえ困難になってゆくリック、エド、コニー、カーロスら。私はホームケア・ワーカーとして、彼らの身のまわりを世話している。死は逃れようもなく、目前に迫る。失われるものと、それと引き換えのようにして残される、かけがえのない十一の贈り物。熱い共感と静謐な感動を呼ぶ連作小説。
著者等紹介
ブラウン,レベッカ[ブラウン,レベッカ][Brown,Rebecca]
1956年、アメリカ生れ。シアトル在住。『体の贈り物』でラムダ文学賞、ボストン書評家賞、太平洋岸北西地区書店連合賞を受賞
柴田元幸[シバタモトユキ]
1954年、東京生れ。東京大学文学部教授。『生半可な学者』で講談社エッセイ賞受賞
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
zero1
114
死は不可避だが救いでもある?ホスピスが存在する意味?エイズ患者のためのホームケア・ワーカーが多くの患者と出会う。女性は最期をどう見たか、11の短編で描く。冒頭の「汗の贈り物」でシナモンロールを用意するのは何故?死を覚悟すると日常のサイクルを保ちつつ死にたいと思うようになるのか。また、恥や怒り(後述)は生きている証。手伝う女性の中に死が蓄積される様も描かれている。静謐という言葉は本書のためにある。レビュー190件と少ないのが不思議な名著。2019/07/09
のっち♬
113
末期のエイズ患者との心の交流がホームケアワーカー視点で、繊細で透明感のある文章で淡々と綴られている。重いテーマでありながらそれに付着しがちな物語性を一切排し、著書の体験に基づいた現場の空気がストレートに伝わってくる。抽象的な表現もなく平易で適格な言葉選びでの丁寧な世界構築、起きたこと、感じたことをシンプルかつダイレクトに綴るその語り口が見事。短編11編の題名は「The Gift of〜」に統一され、作品毎に贈り物も相手も異なるのだがどれも静謐な感動を帯びており、ささやかながら味わい深い贈り物となっている。2020/05/02
のんき
101
ホームケアワーカーと重い病気の人たちとの交流が描かれています。ホームケアワーカーのお仕事は大変だなあ。お風呂とか、着替えとか。異性だとなおさら。わたしにはできないなって思いました。患者さんたちが、自分の身体を動かすこともやっとだけど、ホームケアワーカーさんに、パンを買ってきて用意したり、紅茶やコーヒーを入れたり、懸命にもてなそうとします。わたしは、まあ健康だし、身体を大事にしないといけないな。そして重い病気の患者さんたちのように、今、今日からでも、優しい贈り物をさりげなく、普通にできるようにしていけたらな2019/01/10
NAO
85
エイズの患者のホームケアをする女性を主人公とした短編集。エイズとの闘いは、負け戦のようなところがある。患者の健康そうな友人が、1年もたたないうちに痩せ衰えた患者となって主人公の目の前に現われたりする。そういった姿に主人公は驚き恐れながらも、どこまでも彼らに誠実であろうとする。現状をそのままに綴るために、どこまでも誠実であること。そして、こういった話についつい付着してしまう余計な「物語」を決して受け付けないこと。この作品の文章が、どこまでも淡々としているのはそのためだ。⇒2019/06/02
kana
76
ダメです。。涙が止まりません。人の命に関わる物語だから覚悟はしていたし、終盤まではこらえていたけれど、コニーが「あたしは幸運よね」と言ったところから号泣です。不治の病に苦しむ人たちの心身の世話をするホームケア・ワーカーとして働く女性の物語。介護というのは想像以上にとてもウェットでした。死と向き合う患者と対話するだけでなく、食事、トイレ、お風呂などあらゆる生の営みを手伝うので自然と患者と触れ合い、距離が近づく。単に仕事と割り切れないし、この人はあとどのくらいで死ぬと計算してしまうずるさに苦悩する。(続)2014/04/27