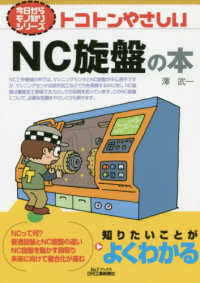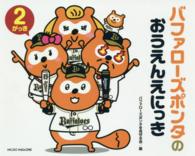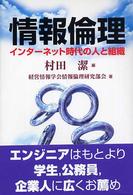内容説明
禁酒法時代のアメリカを去り、男たちはパリで“きょうだけ”を生きていた―。戦傷で性行為不能となったジェイクは、新進作家たちや奔放な女友だちのブレットとともに灼熱のスペインへと繰り出す。祝祭に沸くパンプローナ。濃密な情熱と血のにおいに包まれて、男たちと女は虚無感に抗いながら、新たな享楽を求めつづける…。若き日の著者が世に示した“自堕落な世代”の矜持。
著者等紹介
ヘミングウェイ,アーネスト[ヘミングウェイ,アーネスト][Hemingway,Ernest]
1899‐1961。シカゴ近郊生れ。1918年第1次大戦に赤十字要員として従軍、負傷する。’21年より’28年までパリに住み、『われらの時代』『日はまた昇る』『男だけの世界』などを刊行。その後『武器よさらば』、短編「キリマンジャロの雪」などを発表。スペイン内戦、第2次大戦にも従軍記者として参加。’52年『老人と海』を発表、ピューリッツア賞を受賞。’54年、ノーベル文学賞を受賞。’61年、猟銃で自裁
高見浩[タカミヒロシ]
東京生れ。出版社勤務を経て翻訳家に
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
444
ヘミングウェイの代表作の1つだが、『武器よさらば』や『誰がために鐘は鳴る』などとは小説作法が違う。すなわち本編は、物語としての起伏には乏しく、より小説的な造形法をとっている。小説の最初の舞台は第1次大戦後のパリ。ジェイコブは通信社の特派員であり、同時に作家でもあるのだが(明らかにヘミングウェイ自身を投影している)、彼の周縁にいる人物たちを含めて、人生に明確な目的を持てない。日々、酒ばかり飲む生活を続けているのだが、その対極にあるのが、パンプローナでの闘牛であり、ロメロであった。理由なき退廃と、刹那の光芒⇒2019/10/27
kaizen@名古屋de朝活読書会
128
自分にとってのヘミングウェイの最善三の1つ。 一見、暗そうな話の中に、希望が見えて来るのがヘミングウェイの人間性の証しなのだろう。 スペインに行ったときに,ヘミングウェイの足跡をたどる時間がなかったのが残念。 2013/05/07
ehirano1
126
WWI後のロストジェネレーションを描いた作品とのことで、そんな世代の虚無感の描写は流石と言う感じでした。その意味で、タイトルはポジティヴな意味かと思いきやむしろその逆であるように思いました。そうは言っても、変わらない過去と現在に苦悩するばかりが果たして・・・というメッセージをあったのではないかと思います。2025/01/04
yoshida
111
第一次世界大戦後のパリ。戦傷で身体にとある障害を持つジェイク。束の間の平和の日々をジェイクは通信社の特派員として働く。美貌のブレットと愛し合うも障害もあり結ばれぬ2人。休暇をスペインのフェイスタで過ごすべく、ジェイクと友人達、ブレットと婚約者は落ち合う。読みやすい作品であり、美貌で奔放なブレットに翻弄される男達の苦しみが良く分かる。ブレットが奔放に振る舞わざるを得ないのは、ジェイクと結ばれぬと理解しているから。結ばれないが、離れられぬジェイクとブレット。フェイスタの華やかさとの鮮やかな対比が印象に残る。2021/12/10
nobi
95
「老人と海」は五感に訴え「武器よさらば」は切迫した展開があり「日はまた昇る」は村上春樹も夢中になったようなのに、なかなか乗り切れなかった。ちょっと気の利いた返しもあるパリのカフェでの談笑、微妙な男女関係の描写は第一次大戦後取り戻した日常をいとおしんでなのか。それにしてもワインなど酒量がすごい。カフェを変えてホテルに帰って移動中の汽車で。再会を祝って、塞いだ気分を紛らわす時も。その中サン・セバスチャンでの闘牛のフィエスタの情景が展がってくる。無声映画の時代に言葉で情景を再現しようとするかのような熱気と共に。2024/01/21