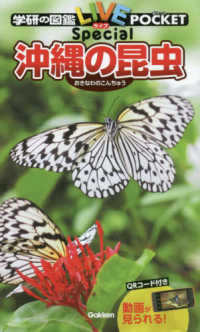出版社内容情報
ドストエフスキー[ドストエフスキー]
著・文・その他
内容説明
世間から侮蔑の目で見られている小心で善良な小役人マカール・ジェーヴシキンと薄幸の乙女ワーレンカの不幸な恋の物語。往復書簡という体裁をとったこの小説は、ドストエフスキーの処女作であり、都会の吹きだまりに住む人々の孤独と屈辱を訴え、彼らの人間的自負と社会的卑屈さの心理的葛藤を描いて、「写実的ヒューマニズム」の傑作と絶賛され、文豪の名を一時に高めた作品である。
著者等紹介
ドストエフスキー[ドストエフスキー] [Достоевский,Фёдор М.]
1821‐1881。19世紀ロシア文学を代表する世界的巨匠。父はモスクワの慈善病院の医師。1946年の処女作『貧しき人びと』が絶賛を受けるが、’48年、空想的社会主義に関係して逮捕され、シベリアに流刑。この時持病の癲癇が悪化した。出獄すると『死の家の記録』等で復帰。’61年の農奴解放前後の過渡的矛盾の只中にあって、鋭い直観で時代状況の本質を捉え、『地下室の手記』を皮切りに『罪と罰』『白痴』『悪霊』『未成年』『カラマーゾフの兄弟』等、「現代の予言書」とまでよばれた文学を創造した
木村浩[キムラヒロシ]
1925‐1992。東京生れ。東京外国語大学ロシア語科卒。出版社勤務の後大学で教鞭をとる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
青蓮
104
本作はドストエフスキーの処女作ということで、彼の作品の中でも比較的読みやすい部類に入るかと思います。小役人マカールと薄幸の乙女ワーレンカの愛の行方は如何に。「貧困」という病理は、未来にあるはずの全ての可能性を蝕んでいく、恐ろしいものだとひしひしと感じました。貧しさがなければ、二人が引き裂かれることはなかっただろうに。一番最後の手紙にあるマカールの悲痛な叫びがとても切ないです。そして現代社会に蔓延しつつある「貧困」についても考えさせられる所がありました。2016/02/24
のっち♬
100
初老の小役人と幸薄な少女の間で交わされる往復書簡という体裁で、寄る辺ない孤独と貧困を抱えた者同士の絆が描かれる。挿話が示唆するように金は必ずしも人を幸福にしないし「貧乏は罪ではない」、しかし、「浮世の気苦労」は「こんなにも人を卑屈にする」し、貧乏は堕落と破滅をもたらす。貧乏で結びついた二人の現実に対する姿勢の違いや温度差は絶妙。それでも献身的な愛情をみせる彼の文面をはじめユーモアとペーソスが随所に生きている。少女の昔話や外套のボタンが落ちる場面、最後の手紙などは印象深い。物質と精神の豊かさを問うた処女作。2018/04/14
ペグ
93
貧しさと当時の社会背景故に引き離される心と心。熱烈な想いと饒舌な言葉(手紙の文章)によって益々熱い。処女作との事だがこの溢れ出る想いをこれだけの文章にしなければ納得出来ないのは、彼自身の体質なのだな〜だからこそのドストエフスキー!2019/08/24
どんぐり
91
ドストエフスキーの処女作。小役人で貧乏を極めるマカール・ジェーヴシキンによる「わたしの可愛い人、わたしのなつかしい人、わたしのいとしい人」と言わしめる薄幸で病弱な女性ワーレンカとの往復書簡。ワーレンカの保護者となり、資金援助をする小役人は常に極貧状態だ。ほつれた一本の糸につながったボタンが服からコロコロと音をたてて転がり、男の身なりがあまりにもみすぼらしいのを見かねた閣下が金を手渡すくだりは爆笑もの。物語はワーレンカが去ることによって終わる。ふーん、イマイチ主題がわからなかったな。2022/10/15
みゃーこ
91
泣きたくなるほど繊細な作品。間違いなく名作2013/11/22
-

- 和書
- さざなみ町とはざまの子
-

- 電子書籍
- 10年先から恋してる【マイクロ】(1)…