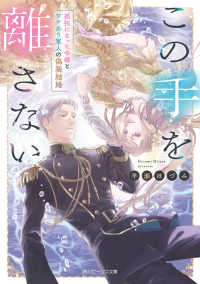内容説明
あらゆるものから自由であり得た子ども時代の貴重な体験を回想しながら、真の幸福とは何かを語る『幸福論』。バーデン湯治中にめぐり会ったユーモラスなはぐれ者のからすに自画像を重ね合せて、アウトサイダーとしての人生を描く珠玉の短編『小がらす』。人間として文学者として、幾多の危機を越えてきたヘッセが、静かな晩年の日々につづった随想と小品全14編を収録する。
著者等紹介
ヘッセ,ヘルマン[ヘッセ,ヘルマン][Hesse,Hermann]
1877‐1962。ドイツの抒情詩人・小説家。南独カルプの牧師の家庭に生れ、神学校に進むが、「詩人になるか、でなければ、何にもなりたくない」と脱走、職を転々の後、書店員となり、1904年の『郷愁』の成功で作家生活に入る。両大戦時には、非戦論者として苦境に立ったが、スイス国籍を得、在住、人間の精神の幸福を問う作品を著し続けた。’46年ノーベル文学賞受賞
高橋健二[タカハシケンジ]
1902‐1998。東京生れ。東京大学独文科卒。’31年ドイツに留学、ヘッセへの7回の訪問を始め、ケストナー、マン、カロッサ等多くの作家と交流。ドイツ文学の紹介、翻訳などで活躍し、読売文学賞、芸術選奨ほかの各賞を受賞
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
aika
60
右にならえ、ができず、アウトサイダーとして生きたヘッセが綴る『幸福論』と題された随想の端々に、神経痛に悩ませられながらも溢れ出る生の実感、そして老齢の哀切と達観とが感じられます。ヘッセの代名詞である『デミアン』や『車輪の下』をそのまま辿っているような、ヘッセ少年と友達との切ない思い出や、ナチスに抵抗した旧友との数十年ぶりの邂逅、ヘッセ文学の愛読者である東京の少年から送られた手紙に対する著者の眼差しの温かさなど、まるで目の前にヘッセその人が佇んでいて、人がらが文章の底から伝ってくるような感覚になりました。2020/07/18
活字の旅遊人
46
14編の短い随筆集。晩年の作であり、裏寂しさと達観が入り交じり、何となく入りづらかった。中ほどにある「小がらす」「マウルブロン神学校生」から急に引き込まれた。「エンガディーンの体験」も共感。続く「過去とのめぐり会い」は、詩についてのネタで始まるのだが、詩を小説に置き換えて読む。ああ、おっしゃる通りです。と反省し、ひれ伏します。表題の「幸福論」を最後に読み返す。ズハリ書ききらないように思うが、やはり「自由」ということなんだろうね。しかも、「安心」に裏付けられている「自由」。「知と愛」への思い入れもすごい。2022/11/12
meg
40
10代の頃から愛読するヘッセの作品。 心が洗われるような美しい文章。幸福のかたちは人の数だけあるのかもしれない。しがらみは振り払いたい。2024/06/17
もちまる
36
ヘッセの随想や手記がメインかな。まだ読んでない本のこともあり、他のを一通り読んだらもう一度読み返そうと思います。2019/06/30
加納恭史
32
ガラス玉遊戯は大書なので読み進まず、少し休み、ヘッセの晩年のこの「幸福論」を読む。初老の彼の作風は変わらない。祖父に似た感じがしていて、若い頃から彼の作品には共感する部分があり、好きだった。「郷愁」から魅了された。彼の感性が良い。「デミアン」や「知と愛」も良かった。初老ともなると、湯治の話がやはり出て来る。若い頃よりも温泉の暖かみが身に染みる。彼はバーデンの温泉が特に好きでよく訪れたよう。最初の話はそこから自宅にトランクを荷づくりして送った時、届かなかったので、大事な中身ごと盗まれたとショックを受けた話。2024/02/15
-

- 和書
- 〈教室〉の中の村上春樹