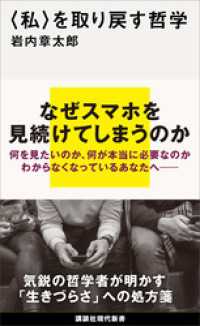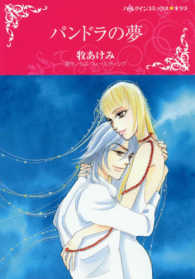内容説明
時は鎌倉時代。武門の身を捨て十三歳で出家した一遍は、一度は武士に戻りながら再出家。かつての妻・超一房や娘の超二房をはじめ多くの僧尼を引き連れ遊行に出る。断ち切れぬ男女の愛欲に苦しみ、亡き母の面影を慕い、求道とは何かに迷い、己と戦いながらの十六年の漂泊だった。踊念仏をひろめ、時宗の開祖となった遍歴の捨聖一遍が没するまでの、波瀾の生涯をいきいきと描く長編小説。
著者等紹介
佐江衆一[サエシュウイチ]
1934(昭和9)年、東京生れ。コピーライターを経て’60年、短編「背」が新潮社同人雑誌賞を受け作家デビュー。「繭」「すばらしい空」などで5度芥川賞候補となり注目された。’90(平成2)年『北の海明け』で新田次郎文学賞、’95年『黄落』でドゥ・マゴ文学賞、’96年『江戸職人綺譚』で中山義秀文学賞を受賞
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
S.Mori
13
時宗を開いた一遍の生涯を描いた小説です。人を救いたいというこの僧の純粋さに心を打たれます。一遍が生きていたのは災害や戦争の続く過酷な時代でした。そんな時になにかも捨てて求道を続けるのは、並大抵のことではありません。性欲に悩まされたことも赤裸々に描かれており、リアリティを感じました。どんな人間もそのことで多かれ少なかれ悩むからです。求道の末に一遍が掴みとった境地は、自分を捨て去ることです。一遍のような生き方は無理だと思いました。でも、悩みや苦しみから逃げない生き方は、少しでも真似したいです。2020/06/13
おか
11
久しぶりに 途中で投げ出したくなった^_^; 仏教のあり様が 色々書かれているが それが又難解。「南無阿弥陀仏」と「何妙法蓮華経」の違い。そして 一遍上人の51歳没迄の 本当に数奇な運命 そして彼の心の変遷が複雑怪奇 というより私から見ると 「自力聖道門」により 五欲から逃げているように思えて仕方なかった。しかし ともあれ 一遍上人は「南無阿弥陀仏」を無心に唱えることにより念仏往生するという信心を確立したのであろう。「踊り念仏」は「盆踊り」の祖なのかしら、、、2016/02/26
目黒乱
7
一遍って女性受けがよかったんやなーと、アホみたいな感想しか浮かばん。2014/12/19
kuribosu
3
他力である念仏者でありながら、禅宗や密教のように、自分を厳しく律し、清く貧しく何もかも執着するものを捨てさり、ひたすら他人の往生を願って念仏を唱え、体力のかぎりを尽くして阿弥陀の来迎のときを迎えるという、本当の聖、真の宗教者の生き様を目の当たりにして、感動した。2018/01/18
うたまる
3
「念仏には仏と人との二つはありません。(中略)念仏が念仏を申し、名号が名号をきくのです」……時宗の開祖、一遍上人の生涯。その教義の核心は、浄土宗、浄土真宗の延長線上にあり、徹底的に自力を削いでいくことのようだ。それは欲を振り払いたくてもできなかった一遍自身の諦めの境地から来るものであり、時宗が最底辺に寄り添った理由でもありそう。とはいえ、場当たり的というか融通無碍にも見える一遍の心の裡は分からない。発心から教団の発生、その伸長と丁寧に追ってはいても、如何せん300頁足らずの分量では凡愚の身にはちと厳しい。2017/06/19