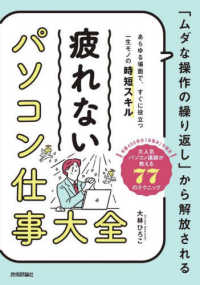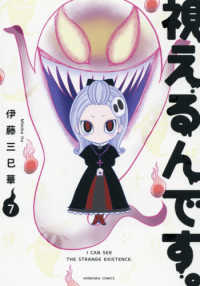内容説明
お茶を習い始めて二十五年。就職につまずき、いつも不安で自分の居場所を探し続けた日々。失恋、父の死という悲しみのなかで、気がつけば、そばに「お茶」があった。がんじがらめの決まりごとの向こうに、やがて見えてきた自由。「ここにいるだけでよい」という心の安息。雨が匂う、雨の一粒一粒が聴こえる…季節を五感で味わう歓びとともに、「いま、生きている!」その感動を鮮やかに綴る。
目次
茶人という生きもの
「自分は何も知らない」ということを知る
頭で考えようとしないこと
「今」に気持ちを集中すること
見て感じること
たくさんの「本物」を見ること
季節を味わうこと
五感で自然とつながること
今、ここにいること
自然に身を任せ、時を過ごすこと
このままでよい、ということ
別れは必ずやってくること
自分の内側に耳をすますこと
雨の日は、雨を聴くこと
成長を待つこと
長い目で今を生きること
著者等紹介
森下典子[モリシタノリコ]
1956(昭和31)年、神奈川県横浜市生れ。日本女子大学文学部国文学科卒業。大学時代から「週刊朝日」連載の人気コラム「デキゴトロジー」の取材記者として活躍。その体験をまとめた『典奴どすえ』を’87年に出版後、ルポライター、エッセイストとして活躍を続ける(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 6件/全6件
- 評価
テレビで紹介された本・雑誌の本棚
- 評価
-





TERU’S本棚
- 評価
-





読書素人本棚
- 評価
新聞書評(2018年)の本棚
- 評価
-





真人生が彩る 『 生命紀 』本棚
- 評価
新聞書評(2020年1月~3月)の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mura_ユル活動
901
筆者は茶道のお稽古を通じ、感じたことをエッセイで綴る。。「土曜の稽古に行きたくないなあ」が何回も出てきては、結局は25年もつづけている。理由は?道具や作法を覚えることなど、がんじがらめのようでいても、自由。冬と夏のお茶の点て方の違い、季節を感じること、五感が磨かれること、個々に習ったことが視点を変えることで、繋がっていく。お茶は、日本人の暮らしの美学と哲学を自分の体に経験させ知ること。教えないことで教えようとする。お茶は「他人」と比べるのではなく、「昨日までの自分」と比べること。2014/04/27
seacalf
856
肩肘張らない素直な文章が茶道の入口へといざなう。作法に雁字搦めで敷居が高そうに見えるお茶の世界も、不器用で等身大の筆者の姿をそのままに書いてくれているので、さらさらと読みやすい。『雨の日は、雨を聴く。雪の日は、雪を見る。夏には、暑さを、冬には、身の切れる寒さを味わう。どんな日も、その日を思う存分味わう。お茶とは、そういう「生き方」なのだ。』読むと、茶道を始めたくなること請け合い。まずは映画を観たいな。すーっと穏やかになり気持ち良く生きるヒントが幾つも見つかるから、この本は好意的に読まれているんだろうなあ。2020/05/11
chinayo
814
お茶の世界がわかる読みやすい本。初日のお稽古から、正直な感想を言ってくれるので、凄くいい!2018/05/13
エドワード
739
多くの若者は茶道が苦手だ。作法が難しく、すぐには解らないからだ。「頭で理解しようとしないで。身体が覚えるまで、練習、練習、練習よ。」と先生は言う。茶道を習うことは、学校の勉強とは対極にある。正解が無い。日々の過ごし方、感じ方に正解が無いからだ。正月に「今年もよろしくお願いします。」と挨拶するのは、「今年も一年、毎日をつつがなく過ごしましょう。」とお互いの息災を祈ることなのだ。四季がめぐり、干支がめぐる、日本の自然を愛でること。毎年同じことを繰り返す喜び。五感で味わう自然。そして、一期一会。それが茶道。2018/10/23
Aya Murakami
731
新潮文庫の100冊2018。 考えるな、感じろ!が主要なテーマだろうか?すぐに答えを求めて質問するのではなくじっくり待つという姿勢も大事だと説いていました。ただ…、今の日本人は答えを求めて質問するということすらできていない気が…。2018/10/07
-

- 和書
- はじめてのクレイケア