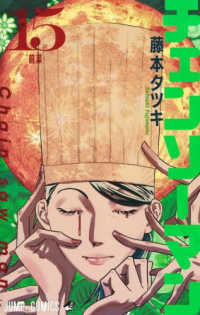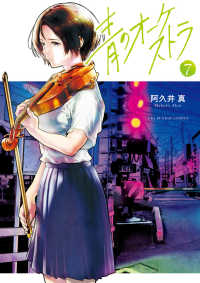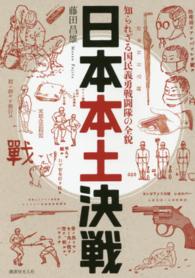内容説明
漱石門下の異才・内田百〓の代表的著作のひとつに数えられるこの随筆集は、昭和8年に上梓されるや大いに評判を呼び、昭和初期の随筆ブームの先駆けとなった。漱石の思い出から自らの借金話まで、軽妙洒脱、かつ飄逸な味わいを持つ独特の名文で綴られた作品群は、まさに香り高い美酒の滋味妙味たっぷり。洛陽の紙価を高めた古典的名著が、読みやすい新字新かな遣いで新潮文庫に登場。
目次
短章二十二篇(琥珀;見送り;虎列刺 ほか)
貧乏五色揚(大人片伝;無恒債者無恒心;百鬼園新装 ほか)
七草雑炊(フロックコート;素琴先生;蜻蛉玉 ほか)
著者等紹介
内田百〓[ウチダヒャッケン]
1889‐1971。本名・内田栄造。別号・百鬼園。岡山市に酒造家の一人息子として生れる。旧制六高を経て、東京大学独文科に入学。漱石門下の一員となり芥川龍之介、鈴木三重吉、小宮豊隆、森田草平らと親交を結ぶ。東大卒業後は陸軍士官学校、海軍機関学校、法政大学のドイツ語教授を歴任。1934(昭和9)年、法大を辞職して文筆家の生活に入った。初期の小説には『冥途』『旅順入城式』などの秀作があり、『百鬼園随筆』で独自の文学的世界を確立。俳諧的な風刺とユーモアの中に、人生の深遠をのぞかせる独特の作風を持つ
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- DVD
- 人妻・OL・女子学生 狙って襲う