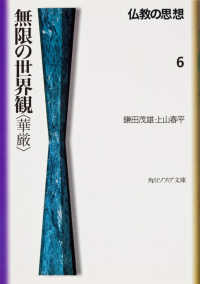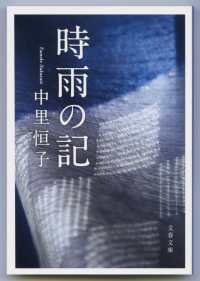内容説明
水涸れ弾尽き、地獄と化した本土防衛の最前線・硫黄島。司令官栗林忠道は5日で落ちるという米軍の予想を大幅に覆し、36日間持ちこたえた。双方2万人以上の死傷者を出した凄惨な戦場だった。玉砕を禁じ、自らも名誉の自決を選ばず、部下達と敵陣に突撃して果てた彼の姿を、妻や子に宛てて書いた切々たる41通の手紙を通して描く感涙の記録。大宅壮一ノンフィクション賞受賞。
目次
第1章 出征
第2章 二二キロ平米の荒野
第3章 作戦
第4章 覚悟
第5章 家族
第6章 米軍上陸
第7章 骨踏む島
第8章 兵士たちの手紙
第9章 戦闘
第10章 最期
著者等紹介
梯久美子[カケハシクミコ]
1961(昭和36)年熊本県生れ。北海道大学文学部卒業。編集者を経て文筆業に。初の単行本である『散るぞ悲しき』は、2006(平成18)年に大宅壮一ノンフィクション賞を受賞、米・英・韓・伊など世界7カ国で翻訳出版されている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 3件/全3件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
462
再読だが、読後はやはり感嘆(栗林忠道とライターの梯久美子の双方に)のため息が漏れる。実に立派な将軍である。私は基本的に軍隊も軍人も嫌いだが、その状況に置かれたときになしうる行為、行動としてこの人に勝る人物はまずいないであろうと思う。栗林にとって、大本営もが早々に切り捨てた硫黄島を死守することは、本土空襲を一日でも遅らせることであり、しかも終戦処理に寄与することであった。そのために自己の生を捧げるにはやぶさかではなかっただろうが、そのために2万人の将兵をむざむざと死なせるのは実に慚愧の思いであっただろう。2018/09/04
おしゃべりメガネ
257
凄まじく、圧巻でした。映画で観たことのある『硫黄島』にこんな真実があったとは、とにかく驚きの連続でした。最大の激戦の地が5日で陥落するという米軍の予想を大きく覆し、36日間も抵抗し、持ちこたえた日本軍を指揮した「栗林忠道」指揮官の活躍を中心に、日本軍をとりまくとてつもない地獄の環境やそれぞれの家族への思いをつづる手紙などを交え、真実の姿をこれでもかというくらいに浮彫にします。もちろん悲惨な状況には間違いないのですが、「栗林」指揮官の常に周囲を気遣い、前線に立ち、共に最後まで戦う姿に勇気づけられました。2016/08/17
ykmmr (^_^)
175
若干、無名気味であったが、映画で取り上げられて、広く名前が知られるようになった一男・一軍人。しかしその実力は、乃木や東郷、山本や牛島などと肩を並べる…いや、考え方によっては、それ以上の実力者なのかもしれない。予想された『玉砕』時間を、遥かに超えて、部下への配慮だけではなく、自分の『拘り』にも力を尽くした。そんな彼も、家族の前では、これも一人の愛妻家・子煩悩な父親で、多忙な中、筆マメと言えるくらいの手紙を認めていた。次女に対する手紙は本当に微笑ましい。妻に対しては、家の窓の調子などを伺う面もあり、2022/07/22
yoshida
175
大東亜戦争の激戦地である硫黄島。硫黄島の陥落はグアム、サイパン、テニアンからのB―29爆撃機による、米軍の日本本土への無差別爆撃を許す事となる。硫黄島総指揮官の栗林忠道は一般市民が虐殺されるのを防ぎ、米国内の厭戦気分を煽り講和の時間を作るために玉砕を禁じ長期持久作戦を選ぶ。マリアナ沖海戦に破れた日本海軍の聯合艦隊は事実上壊滅し、制海権と制空権も喪われ大本営は硫黄島を早々に放棄する。硫黄島では敢闘36日に及ぶ。将兵の様々な想いを込めた栗林の訣別電報も大本営は改ざんする。硬直した組織により多大な犠牲が残った。2016/04/16
遥かなる想い
150
大宅壮一ノンフィクション賞受賞。第二次世界大戦の激戦地硫黄島で散った司令官栗林忠道を残された手紙を通して描いた作品。戦後生まれの我々には硫黄島の戦いと言われてもピンとこないが、5日で落ちるという米軍の予想を大幅に覆し36日間持ちこたえた地獄の戦いだったようだ。労作とも言える取材が我々が知らなかった日々を教えてくれる。2011/02/13