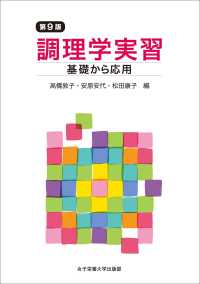出版社内容情報
小学校5年生の魚彦が、臨死の森で偶然知った転校生・海子の秘密。夏の暑さに淀む五反田で、子どもたちの神話がつむがれていく。
魚彦。僕の変な名前は、お母さんの初恋にちなんでつけられた。写生大会で行った臨死の森で、転校生・海子の秘密を見てしまう。二人だけの秘密。夏の海の水の音。色ガラスの破片。車椅子の今田は魔法使いに会ったという。そんなの嘘だ、嘘であって欲しいと僕は思う。出処の知れない怒り、苛立ち、素晴らしい遊び、僕はこの楽園を飛び出したいのかもわからない。あの神話のような時代を。
内容説明
魚彦。僕の変な名前は、お母さんの初恋にちなんでつけられた。写生大会で行った臨死の森で、転校生・海子の秘密を見てしまう。二人だけの秘密。夏の海の水の音。色ガラスの破片。車椅子の今田は魔法使いに会ったという。そんなの嘘だ、嘘であって欲しいと思う。出処の知れない怒り、苛立ち、素晴らしい遊び、僕はこの楽園を飛び出したいのかもわからない。あの神話のような時代を。
著者等紹介
前田司郎[マエダシロウ]
1977(昭和52)年、東京都五反田生れ。’97(平成9)年、劇団「五反田団」を旗揚げする。2008年、『生きてるものはいないのか』で岸田國士戯曲賞、’09年、小説『夏の水の半魚人』で三島由紀夫賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
194
前田司郎は初読。プロの作家にしては拙劣ともいってもいいような文体だ。ご本人もそのことを重々自覚していると思われる。そこで選ばれたのが、小学校5年生の男の子を語り手に選ぶという方法だったのだろう。そして、それはここではかなりの程度に成功している。品川区の一角に終始する行動半径の狭さは、まさに小学生の世界だ。私たちは、一昔前の小学生の「リアル」を追体験することになる。エンディングはことさらに印象的だが、何も解決しないことに不満な読者もいるかもしれない。しかし、それこそがこの作品を小説として成立させているのだ。2015/03/31
新地学@児童書病発動中
119
消費税が3%だった頃の小学生のリアルな感情を描いた小説。三島由紀賞受賞作。あまり期待しないで読み始めたのだが、非常に気に入った。この小説の一番の特長は子供の視点で物語が進行していくところだ。友達づきあい、学校生活、女の子に対するほのかな憧れなどが、主人公の小学5年生魚彦の視点で書かれているので読者は小学生に逆戻りして、子供の頃の感情に浸りきることができる。現実の世界のことを描いていた物語が、海を間近にして幻想的なものに変わる結末が見事で、その余韻は読んだ人の胸の中にいつまでも響き続けるだろう。2015/03/20
優希
51
夏の神秘がこめられているような作品だと思いました。それは夏の楽園でもあり神話のようなひとときなのです。2023/07/08
sin
45
思い出したよ!自意識は苦しい。僕が僕がと胸の奥にざわめきつづける。僕をみて(傷つけたい)僕に構うな(いっそ滅茶苦茶になってもいい)、そして誰もがこころのなかで叫んでいるんだ!愛しているが解らなくて「愛してくれ」という子供たち?そしていまでも訴え続けている「解って欲しい」と、ただそれだけを…2014/06/18
えりか
44
魚と話せるお母さんをもった小学生の僕、魚彦。魚彦とは母親の初恋の相手の名前。つまり、ハマチ。子供は子供社会の中で必死だ。「こうするとみんなにかっこいいと思われるから、別にしたくはないけどする」みたいな行動基準なのだけど「でも本当は自分がしたいからしてる」ってとこまでは気づかないのも、また子供だからなのだろう。その考えすぎる思考が子供時代の息苦しさと無邪気さなのかもしれない。単純に考えるのは、複雑に考えるよりも難しいものだ。ラストの海のシーンが美しくて切なくて、胸を締め付ける。前田さんの作品もっと読みたい。2018/04/28
-

- 和書
- 三国志の女たち