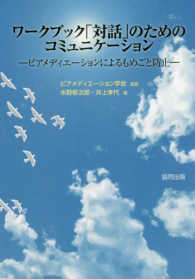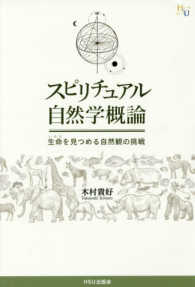内容説明
馬や駕篭、旅篭の使い方を知り、旅支度をととのえたところで、さあ東海道に踏み出そう!街道をゆくのは、商人、職人、武士ばかりではない。お伊勢参りに向かう女性や小僧、そして信心深い犬の姿も?大名行列とすれ違い、箱根の関、難所・大井川を越え、目指すは京都・三条大橋―。仔細な解説と約百点の図絵から、東海道五十三次の実像が見えてくる。
目次
序章 旅好きだったご先祖
第1章 江戸の旅に出る前に(東海道の交通事情;東海道の宿泊事情;旅の支度)
第2章 女も子供も旅に出る(一生一度は伊勢参り;女性も自由に観光旅行)
第3章 東海道五十三次を歩く(東海道の旅程;いざ、出立;箱根の関所を越える;富士山と歩く;大井川を渡る;中間地点を突破;京都まで、あと七宿)
終章 旅を支えた江戸の平穏
著者等紹介
石川英輔[イシカワエイスケ]
1933(昭和8)年、京都府生れ。’76年、『SF西遊記』で作家としてデビュー。印刷技術研究者の貌も持ち、武蔵野美術大学で印刷学の講義を19年間担当した(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かっぱ
39
【図書館】京都~東京間の東海道新幹線に乗りながらの読了。江戸人はこのルートを約15日間ほどをかけて歩んだ。やたらとあちこちへ出かけるのが好きだったご先祖さま達の血は現代の我々にも受け継がれているようです。名所絵図などに描かれもいるが江戸時代の東海道は左側通行。当時のヨーロッパにはこのような決まり事はなく道路での事故が絶えなかったそう。旅の賃金、持ち物、服装など当時の風俗についての解説を交えながら進んでいくので、まさに江戸人と一緒に旅をするような気分にさせられる。好著。2017/12/23
chisarunn
8
近々、徳川美術館へ行ってこようと思うのだが、いま企画展が広重である。なのでちょびっと予習。石川先生の文章が面白いのももちろんだが、図版も多く記憶にブラシをかけるのにも最適なこの本、関係ない部分は読み飛ばそうと思ってたのにやっぱり面白く堪能しました。2022/05/01
sasha
3
前半は江戸時代の旅支度。持ち物や服装、旅費の解説。後半は江戸日本橋をスタートして京都三条大橋までの53の宿場を紹介。当時の風俗なども説明されており面白かった。前半のお伊勢参りの話が好きだな。大人の男女は勿論だけど子供が家出してお伊勢参りって…。今じゃ絶対無理だろう。江戸時代って治安がよかったんだなぁ。しかも犬までお伊勢参り。あぁ、歩いて行ってみたいけど無理だろうなぁ。2012/11/10
あさ
3
たくさんの図も入り、宿場も風俗も具体的で面白かった。江戸時代が階級社会で窮屈だと決めつけられることに凄く抵抗していたけど、読み手はそんな人ばかりではないのでは?とはいえ関所抜けや廻り越しが半ば公然と行われていたというのは意外だったし、自由な旅の雰囲気に驚かされたことも確か。女性の紀行文が少なくつまらないのは残念だな。2012/01/04
本命@ふまにたす
2
近世の旅と東海道に関するエッセイ。内容ももちろん興味深いが、それ以上に図版が多数掲載されているのがよかった。モノクロなのが少し残念。2022/01/31
-

- 和書
- 神の風景 断想