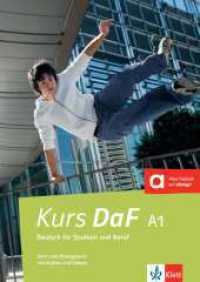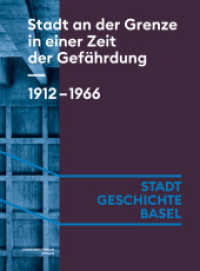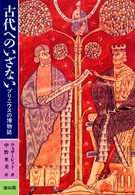内容説明
「文学」それは人間の意識が「言葉」を手段として生み出したもの。そして「言葉」は人間の「身体」が生み出したもの。しかし日本人は江戸時代以来「身体」を「言葉」から切り離し抑圧してきた、なぜなら―。芥川、漱石、鴎外、小林秀雄、大岡昇平、深沢七郎、石原慎太郎、三島由紀夫らの作品を「身体」の切り口から読み替え、文学を含めた全ての「表現」の未来を照らす画期的な論考。
目次
身体の文学史
芥川とその時代
心理主義
文学と倫理
身体と実在
自然と文学
深沢七郎ときだみのる
戦場の身体
太陽と鉄
表現としての身体
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うつしみ
14
江戸の「型」の社会から既に我が国における身体性の排除が始まっていたとする。明治期に欧米流の心理が付加され、文学的には自然主義として流行するが、人間の心理を自然と呼ぶ事に筆者は疑義を表明する。そこを敏感に察したのが大正期の芥川で、彼は今昔物語に中世的brutalityの美を見出した。それは九相図に描かれた様なありのままの身体性の再発見だったが、それは「文明」社会からすれば危ないものでもある訳で、彼の小説も結局は大正風の心理的加工を施されたものに落ち着いている。2025/01/14
まあい
4
近現代の日本文学から、日本人の身体観を読み解く。文学から当時の社会を解析するという、ある意味社会学的な視点の評論で、ときどき出てくる「脳化」という語も近代化(あるいは近代的社会化?)とほぼ置き換え可能。養老孟司の言う「身体」とは、おそらく大塚英志が「マンガには身体性が欠如している」と言うときの「身体」と同じだろう。だとすれば「身体のマンガ史」は果たして不可能なのだろうか?2017/01/24
海螢
2
語られる文脈の知識が乏しくより難解に感じた。要再読。2017/03/14
寛理
1
☆☆☆ 昔、伊藤計劃が絶賛してたので今さらながら読んでみた。かなり雑な評論だが、日本の身体軽視はむしろ江戸時代以来の話だと言ってて面白い。大岡昇平の「事実」という語に注目しているところもあり、よい。2020/03/22
ハイザワ
0
存在と身体性の問題は絡み合っているはずだが、近代文学ではそれが個人の精神とのみ関わって論ぜられていた。 言葉の世界を捨て肉体の世界に沈んだ三島への言及でこの論考は締めくくられるが、それは身体回帰の可能性を暗示させるどころか、余計に身体を文学から遠ざけているようにも感じる。果たして可能性は開けているのか?2015/08/08