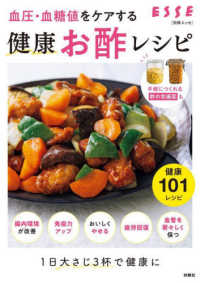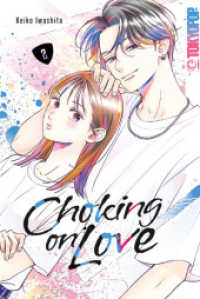内容説明
旬の鱸や真鯛は煎酒で食すのが粋。夏は砕いた氷を入れた霰酒を嗜む。採れたての松茸は丸ごと焼いて、昆布の味噌漬けを土産に。化政文化が花開いた頃、贅を尽くした料理と風流なもてなしで頭角を現し、文人墨客にも愛された日本橋の料亭「百川」。幕末には黒船一行を迎える饗宴を任された名店の運命とは。古今東西の食に通じた著者が解き明かす、江戸料理の真髄!
目次
第1章 日本橋浮世小路「百川」界隈
第2章 大田南畝と「山手連」
第3章 「百川」の粋な酒肴と贅の極み
第4章 史上最大の饗宴と「百川」の消滅
著者等紹介
小泉武夫[コイズミタケオ]
1943(昭和18)年、福島県の酒造家に生れる。東京農業大学で教授として永く教鞭を執った後、現在は発酵学者・文筆家として活躍中。農学博士。専攻は、醸造学、発酵学、食文化論。学術調査を兼ねて辺境を旅し、世界中の珍味、奇食に挑戦する「食の冒険家」でもある。単著だけでも140冊を超える(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ぶち
100
"発酵仮面"の小泉武夫さんが、江戸日本橋に在った料亭"百川"を紹介してくれます。文人墨客に愛された百川の紹介ですから、単なる料理の紹介に留まらず、江戸の文化や風俗などもたっぷりと紹介されています。もちろん、紹介されている贅を尽くした料理は垂涎ものだし、その風流なもてなしは江戸の粋もここに極まれりという感じです。驚いたのは、あの黒船来航のペリー一行を招待した宴の料理を百川が用意したことです。アメリカ側300名、日本側200名の計500名の料理を、あの冷蔵庫もない時代に拵えたとは本当にビックリです。2021/04/21
佐島楓
67
江戸時代の洗練された食文化の発信基地とも呼ぶべき料亭「百川」。太田南畝や山東京伝も通い、夢中になったとされる贅を尽くした料理の数々。実在したこの料亭のことはまったく知らなかったため興味深く読んだ。ペリーも歓待したほどの力を持った料理店だったのに、なぜか明治期に姿を消してしまうというミステリ要素もあって面白い。テキストでしか知らないような当時の戯作者への親近感が少し増した。2019/06/05
saga
34
古典落語『百川』は落語ではよくある虚構だと思っていたら、実際に江戸の名店として実在していたことに驚いた。ならばと言うことで本書を読むと、幕末に活躍した太田南畝などの文人墨客が出入りしていた高級料理屋だったことがわかる。旬の魚介や野菜などを、冷蔵庫がない時代に贅を凝らして調理して提供。しかも、黒船で来日したペリー艦隊一行を饗応したのが百川なんて、更に驚き。八百善や嶋村が今に続いているのに、百川は謎めいた終焉を迎えている。せめて圓生の『百川』を聞くとしよう。2019/06/14
冬見
12
日本橋に店を構えた料亭百川を中心に繰り広げられる、大田南畝と愉快で粋な仲間たちによる「食」の世界。蘭引といい、浮世之煎酒といい、京伝先生がすてき文化人過ぎる。 蘭引の催しに蓬と菖蒲を持ち出す京伝も、抽出したエッセンスをお風呂に仕込む茂左衛門もおしゃれ。洒落た人しかおらん。浮世之煎酒も、こんなふうに真剣に食の探求する姿勢が粋だし、豊かな世界だなあと思う。京伝が経験則から精進節を勧めたくだりが熱かった。山手連のような人々を受け入れた茂左衛門の懐の深さが文化を育んだのだなあ。場って大事だ。2022/01/06
T-top
11
「べらぼう」に百川が出てきた気がして積ん読山を見てみたら、ありました。大田南畝や山東京伝は常連だったとか。百川の贅を尽くした料理もさることながら、大田南畝のサロン「山手連」がよい。新しい煎り酒のレシピ考えたり‥知的なお遊び。煎り酒、買っちゃいました。うまうま。落語「百川」、あったねえ。また点が繋がった!当時の食材や物流も分かって、理解が深まりました。極めつきはペリー艦隊のお接待!ケタ違いの江戸時代の高級料亭でした。煎り酒で白身の刺身食べながら、雰囲気を味わってます。2025/10/16
-

- 和書
- 三つの星 銀の鈴文庫