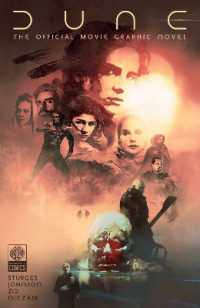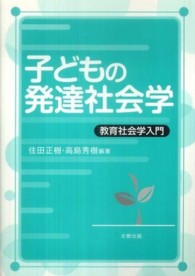内容説明
祖父が死んだ。あの戦争を「生き延びたせいで見なくていいものをたくさん見た」と語っていた元二等兵の遺灰を故郷の海へ還すため、孫の秀二は沖縄を訪れる。そこで手にしたのは、古びた四本のカセットテープ。長い時を超え、その声は語り始める。かつて南の島に葬られた、壮絶な個人的体験を―。敗残兵の影、島民のスパイ疑惑、無惨な死。生への渇望と戦争の暗部を描く、力作長編。
著者等紹介
蓮見圭一[ハスミケイイチ]
1959(昭和34)年、秋田市生れ。立教大学卒業後、新聞社、出版社を経て作家に。2001(平成13)年のデビュー作『水曜の朝、午前三時』がベストセラーとなる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
eipero25
14
カセットテープに吹き込まれた元軍人の語る沖縄での終戦直前のできごと。米兵よりも日本兵の方がたちが悪い。胸糞悪い。当時のことを事細かに語るが、小説としては何か物足らない。現代の秀二君がアカと呼ばれることから始まるが、それについては放りぱなしだし、登場人物が多い上、祖父、山岡、前島、木山らの戦後がもひとつわからず消化不良。その辺が永遠の0にはなれなかった理由かも。2017/09/06
珂音
14
終戦間際、沖縄本島から離れた小島で繰り広げられた壮絶な戦い。 島民にとって本当に恐ろしい敵は迫ってくるアメリカ兵ではなく統制を失い敗走する日本兵だったのではないだろうか。 立ち読みしてたけど直ぐに真剣に読み始め購入。戦争物を一気読みしたのは初めてです。2011/08/11
ひねもすのたり
10
『水曜の朝、午前三時』で1970年の大阪万博を描いた蓮見圭一さん。 本書で描かれるのは1945年の沖縄です。 沖縄戦で現地の民間人が米軍以上に恐れていたのは敗走した日本兵だったというのを読んだ記憶がありますが、本書もそこに力点を置いています。 現代の若者が祖父の時代の戦争を知り、それが自らの生とも深く関わっていることを認識するという点では『永遠のゼロ』に似ています。 ただ、私の読解力のせいもあるとは思いますが、脇を固める登場人物がごちゃごちゃで、修二(若者)の祖父の存在感が希薄だったのがザンネンでした。 2014/10/30
さくらんぼ(桜さんと呼んでね)
9
祖父が亡くなり遺灰を故郷の海へ還すため沖縄を訪れる。そこで手にした4本のカセットテープ。そこで語られていたのは、終戦間際の沖縄の離島で起こった凄惨な出来事だった。島にたどり着いた兵隊の傍若無人な態度、島民のスパイ疑惑、子供相手でも容赦しない。アメリカ兵よりも日本兵の方が恐ろしかった。テープの内容と出だしのアカと呼ばれることとは全然繋がらないように思う。登場人物も多く誰が誰だかわからなくなるし、祖父の存在も希薄。消化不良だけど再読はしたくない。「水曜の朝、午前三時」ほどの素晴らしさは感じられなかった。残念。2018/05/18
やーるー
9
祖父の遺灰を故郷の海へ還すために訪れた沖縄で手にしたカセットテープから語られる、第二次大戦敗戦直前のころの沖縄での個人的体験を通じて、自分という生に脈々と続いていることを再認識していく物語。長閑だった島が、米兵を騙し討ちにしたり、スパイ狩りとして少年を殺したり、仲間割れによる殺戮があったりと、けして気持ちの良い小説ではない。現代と過去をクロスオーバーすると小説としては良かったかな。医者はただの役割でいくらでも交換が利くという一節には共感。自分が誰かにとってかけがえのない人間となれるかそれが一番大事なこと。2013/12/15