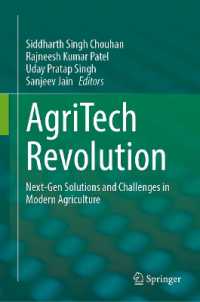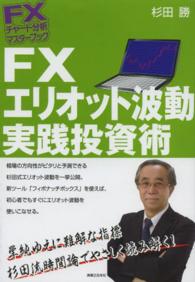内容説明
一体のミイラと英語まじりの奇妙なノートを残して、ひとりの老女が餓死した―老女の隠された過去を追って、人の生き方を見つめた「おばあさんが死んだ」、元売春婦たちの養護施設に取材した「棄てられた女たちのユートピア」をはじめ、ルポルタージュ全8編。陽の当たらない場所で人知れず生きる人々や人生の敗残者たちを、ニュージャーナリズムの若き担い手が暖かく描き出す。
目次
おばあさんが死んだ
棄てられた女たちのユートピア
視えない共和国
ロシアを望む岬
屑の世界
鼠たちの祭
不敬列伝
鏡の調書
著者等紹介
沢木耕太郎[サワキコウタロウ]
1947(昭和22)年、東京生れ。横浜国大卒業。ほどなくルポライターとして出発し、鮮烈な感性と斬新な文体で注目を集める。『若き実力者たち』『敗れざる者たち』等を発表した後、’79年、『テロルの決算』で大宅壮一ノンフィクション賞、’82年には『一瞬の夏』で新田次郎文学賞を受賞。常にノンフィクションの新たな可能性を追求し続け、’95年、檀一雄未亡人の一人称話法に徹した『檀』を発表
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
遥かなる想い
94
もしかしたら、沢木耕太郎は、本書のような本を書くために、他の本を書いているのでは、と思うことがある。私はあまり興味ないが、文体が違う気がする。2010/05/08
速読おやじ
52
沢木さんの若き日のルポ集。昭和52年当時の社会問題を深く揺さぶろうとする。どのルポも時代を感じさせるのだが、登場人物の言葉は生々しい。日ソ共同宣言当時の北方領土関連の話などは興味深かった。返還を望んでいない人々がいるという話は今は書けないのではないか。また不敬列伝という当時の昭和天皇や皇太子に対する投石等の事件の当事者へのインタビューも、今考えると凄い話だ。沢木さんの書き方がそうさせるのか、まるで今ここで起きているかのような、その人物が今話しているような感覚になる。タイトルの人の砂漠がまたいい。2022/04/12
Y2K☮
39
初期の作品集。著者があまり顔を出さない従来のスタイルで文章も若い。一方で扱う題材はなかなか挑戦的。不敬罪、老詐欺師、元娼婦の暮らす施設、相場師など。与那国島と沖縄本島、台湾、そして本土の関係性に纏わる考察や近隣で生活する者が語る「北方領土返還論」に対する本音も興味深い。一般メディアの報道はつくづく大雑把で一面的だなと実感した。一定期間現地で暮らし、直接話を聞くフィールドワークを経て書かれた社会学的ルポルタージュは、オンラインで何でも見られる今こそ絶対的に必要。取材対象に肩入れし過ぎない信頼できる書き手も。2021/08/25
みのゆかパパ@ぼちぼち読んでます
36
70年代後半に出版された沢木耕太郎のルポルタージュ集。取り上げられたテーマは多岐にわたるが、どの作品も丹念な取材によって見知らぬ世界に引き込む力があり、その時代を生きた人たちの生の思いが伝わってきて面白かった。とりわけ、「北方領土」と目と鼻の先で暮らす歯舞の人たちの話は、建前の報道からは見えてこない領土問題の複雑さが垣間見え、これまでの自分になかった視点を与えてもらった気がした。30年前の作品でありながら現代の日本が抱える問題にも通じることが多々あり、単にルポの傑作として以上の味わいがある一冊だと思った。2011/10/17
けぴ
35
天皇一族に対して投石、パチンコ玉、発煙筒など行った不敬罪を犯した人物に取材を試みる『不敬列伝』は著者らしい一作。実際に会うことが叶わなかった人物も多く、そのあたりが未消化な読後感になった。「自民党がどないにがんばっても、物の値段が上がるのを止めることはできません。世界ではこれから人口が増えて、食糧がどうやっても足らんという時代に入るんですよ。天候や環境がガタガタになって…」(P373)50年前の作品なのに見事に現在の世の中を予感している。一番面白かったのは見事な詐欺のおばあさんの『鏡の調書』!憎めない!?2025/10/31
-

- 電子書籍
- ふるさとへ 編集者・甲斐良治の文章