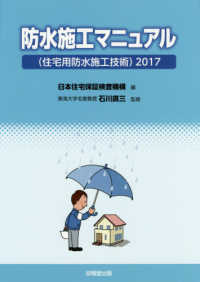内容説明
祖父・幸田露伴の薫陶を受け、着物を粋に着こなした母・文。懐しい着物には、母の気性が表れ、想いがこめられている。没後十年、娘はその着物を自分なりに着ようと思い立つ。露伴愛用の羽織を活かし、母が遺した白生地に色を挿す。着物を蘇らせる様々な職人の技を知り、その工房をたずねる。着物にまつわる細かい手仕事のひとつひとつを丁寧に辿り、世代を越えて愛着をもって着継いでいく悦びを伝える。
目次
とりあへずの箱
透かない単衣
蝋たたき
墨流し
春を待つ
着ぬいた末
順送り
洗い張り
色移る
雪晒し
白に還る
絹の表情
お召機
帯あれこれ
福を着る
「きもの」のことなど―あとがきにかえて
著者等紹介
青木玉[アオキタマ]
1929(昭和4)年、東京生れ。祖父は幸田露伴、母は幸田文。東京女子大学卒。’59年医師青木正和と結婚。’90(平成2)年に母が没してのち、『崩れ』『きもの』『木』『季節のかたみ』などの遺稿の整理と、『幸田文全集』の編集に携わる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
りつか
3
母から借りていた一冊。着物に興味が出たと話したからか、はたまた幸田文の文章が好みだと話した流れで貸してくれたんだったか、記憶はかなり怪しいものの、読み始めたらするすると読み切ってしまった。著者は幸田露伴の孫で幸田文の娘さん。亡くなった母の着物の始末について綴られているのだけれども、着物を作るのに用いられた様々な技術の細かさ、職人さんの仕事の丁寧さにほうと息をつくばかり。麻を雪に晒すなんて知らなかった! こんなに素晴らしい技術の数々が、後継者不足で失われようとしているのは寂しい。家にある着物、もっと着よう。2018/03/18
すう
3
着物を着尽くして着尽くして、やっとたどり着ける領域を垣間見れた気がします。母(幸田文)の残した着物を自分流に直し、また気持ちまでも受け継いでいく。なんて理想的な関係なのだろうか。玉さんはいろいろと謙遜して書かれているが、私などからしたら及びもつかない知識とセンス。こうなれたら素敵だなぁ。2010/06/25
さんとのれ
2
親から譲られた着物がいづれは娘へと、染め直したり仕立て直したりしながら代々受け継がれていく。着物っていいなあ。2016/05/06
てくてく
2
母、幸田文の残した着物を取り出してきて、自分用にあるいは自分の娘用にと加工する作業を通じて、着物を選ぶ眼や、着物を維持するための工夫、職人の技術などを紹介した本。年相応の着物を身にまとう事、次の世代に残すことは大事だろう思うものの、その維持の大変なことを思うと、どうも私は着物は好きだけれども、自分で着て楽しむ、ということはできないままに終わりそうだ。2014/09/14
ゆうがた
2
1枚の着物と、ほどいたり、染め替えたりしながら長いときを経て付き合う。ツーシーズン袖を通せばせいぜいの、使い捨ての服ばかりに囲まれていることに気づかされハッとした。2010/06/11