内容説明
渡辺儀助、75歳。大学教授の職を辞して10年。愛妻にも先立たれ、余生を勘定しつつ、ひとり悠々自適の生活を営んでいる。料理にこだわり、晩酌を楽しみ、ときには酒場にも足を運ぶ。年下の友人とは疎遠になりつつあり、好意を寄せる昔の教え子、鷹司靖子はなかなかやって来ない。やがて脳髄に敵が宿る。恍惚の予感が彼を脅かす。春になればまた皆に逢えるだろう…。哀切の傑作長編小説。
著者等紹介
筒井康隆[ツツイヤスタカ]
1934(昭和9)年、大阪市生れ。同志社大学卒。’60年、弟3人とSF同人誌“NULL”を創刊。’65年、処女作品集『東海道戦争』を刊行。’81年、『虚人たち』で泉鏡花文学賞、’87年、『夢の木坂分岐点』で谷崎潤一郎賞、’89(平成元)年、「ヨッパ谷への降下」で川端康成文学賞、’92年、『朝のガスパール』で日本SF大賞をそれぞれ受賞。’97年、パゾリーニ賞受賞。2000年、『わたしのグランパ』で読売文学賞を受賞。’02年、紫綬褒章受章。’10年、菊池寛賞受賞。’17年、『モナドの領域』で毎日芸術賞を受賞。著書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
優希
99
老人文学としてジャンルが確立されていると思いました。一人暮らしの老人・儀助の日常が淡々と語られていくうちに、何者か分からない「敵」が現れる。何が幻で何が現実かが分からなくなる世界観が老いというものかとぼんやり考えさせられます。細かい日常を軸に、物語が展開していくにつれ、「死というものが見えるようでした。ナンセンスながらも物哀しさが流れているのを感じます。意識の深層にあるものが残酷に炙り出された作品だと思いました。2016/01/27
ケンイチミズバ
90
とある大学教授の定年後。先に逝ってしまった妻にまた会いたい気持ち、そこに佇んでるような錯覚など老境に至った男ひとりの心境も妄想や夢とともに上手く表現されてる。にしても、筒井先生、美貌の教え子を夢想しての自慰行為を妻に見られたらどうしようって。私はあまり長生きしない気がする。いろんなことがしんどい。気力の衰えを感じている。家族以外の人間関係は会社の同期だけかな。お酒や麻雀、旅行のお誘い。後はネットのコミュニケーションくらい。それが敵からの攻撃だったらどうしよう。動揺するほど意味不明な書き込みはないけど。2024/11/14
路地
54
映画化の話題に触発され手に取った。悠々自適で洗練された生活ではあるものの俗物的な面も省略せず生身の老人の生活がリアルに描かれる。一昔前に書かれた小説なので、当時の生活スタイルを読める楽しさもある。あとがきを読んで「敵」の正体は近づいてくる死であることを知り、物語の後半で夢と幻からなるストーリーが加速度的に増えていったことに合点がいく思いだった。2025/06/24
こばまり
46
映像化作品を観るために再読。75歳独居男性の日常がかくもカラフルとは。初読の頃より圧倒的に面白く感じた。映画の方は善戦というか、あれはあれで面白かったが原作の緻密さには遠く及ばず。映画化が原作を凌駕したのは「ショーシャンク」くらいかもと思ったり。2025/10/16
そうたそ
34
★★★☆☆ 静かなる老人文学というところか。仕事も退職し、妻にも先立たれ、独り身で悠々自適の余生をおくる老人渡辺儀助の日常が淡々と描かれる。注目すべきはその日常における細部まで徹底した描写が貫かれているところである。現実が非現実へと向かっていく様は死へ近づいている風も思わせられる。夢の描写が多くなるあたり、「夢の坂分岐点」辺りから夢への興味を作品に反映してきた傾向が断筆宣言解除後のこの作品にも残っているように思う。淡々とした描写が続くが、不思議と飽きずに読み進められるのはさすがの筆力であろう。2017/11/06



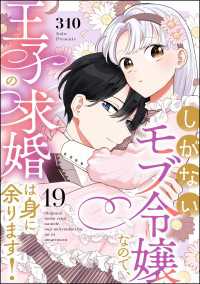
![〈発達協会式〉ソーシャルスキルがたのしく身につくカード 〈2〉 こんなときどうする? [実用品]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/47726/4772613609.jpg)


