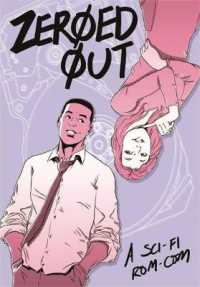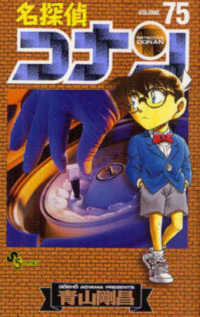内容説明
もっと、人生を強く抱きしめなさい―。私たち一人ひとりが、それぞれの“踏絵”を持って生きている。キリスト教禁教の時代に踏絵に足をかけ、誰に語られることもなく歴史の中へ葬り去られた弱き人々に声を与え、その存在を甦らせた不朽の名作『沈黙』の創作秘話をはじめ、海外小説から読み解く文学と宗教、愛と憐れみ、そして人生の機微と奥深さを縦横に語った、時代を超える名講演録。
目次
人生にも踏絵があるのだから―『沈黙』が出来るまで
文学と宗教の谷間から(交響楽を鳴らしてくれるのが宗教;人が微笑する時;憐憫という業;肉欲という登山口;聖女としてではなく;あの無力な男)
強虫と弱虫が出合うところ―『沈黙』から『侍』へ
本当の「私」を求めて
著者等紹介
遠藤周作[エンドウシュウサク]
1923‐1996。東京生れ。幼年期を旧満州大連で過ごし、神戸に帰国後、11歳でカトリックの洗礼を受ける。慶応大学仏文科卒。フランス留学を経て、1955(昭和30)年「白い人」で芥川賞を受賞。一貫して日本の精神風土とキリスト教の問題を追究する一方、ユーモア作品、歴史小説も多数ある。’95(平成7)年、文化勲章受章。’96年、病没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
優希
58
時代を感じさせない講演集でした。キリスト者だからか、言おうとしていることがスッと入ってきます。名講演ですね。2021/06/08
ジョンノレン
55
勝手な先入観、宗教臭さと人を食った喋り口のせいなのか私は遠藤周作氏が何故か苦手で、その作品を1冊も読んだ事がない。それが何故か図書館で、背表紙に呼ばれたように手に取ってしまった。新潮社主催の同氏の「沈黙」「侍」「スキャンダル」等の自作紹介と外国文学におけるキリスト教をテーマにした全9回の講演会の書き起こしだ。同氏の軽妙な話術は見事で、(会場笑)の部分では否応なく横隔膜が揺れた。各テーマとも無理なく周辺から進め、深掘りして核心を抉り取りにかかる。無宗教の私には違和感を覚える表現もあったが、それなりに納得。→2022/10/28
yumiha
43
『沈黙』の原作も映画も、根性ナシの私には怖ろしいものだった。うっかり思い出して悪夢に引きずり込まれないように要注意!の作品だった。でも本書を読んで、そんな根性ナシの私でもいいと肯定してもらった気がした。何しろ作者自身によれば、「神の沈黙」だけではなく、踏絵を踏んでしまったがゆえに歴史から葬り去られた人々の「沈黙」も意味したタイトルだったからだ。また本書の〈神様を一番わかるのは、聖人を除くと、罪びとだ〉という箇所にグッと来て、これまで教条的道徳的と思って来たキリスト教が身近に感じられた。根性ナシもOK.2021/08/29
活字の旅遊人
42
遠藤周作先生のフランス文学、キリスト教文学、そして自著にまで及ぶ講演録。『沈黙』『侍』『わたしが・棄てた・女』『スキャンダル』などの制作過程や思考にしても言及されており、なお一層興味深い。ご自身が分析される遠藤作品の魅力。どこまで言うのか、難しいですよね。この謙虚な姿勢を保ちながらの自己主張は、いろいろなところで参考になりそうだ。また、フランス文学、キリスト教文学講義についても実に面白く、深い。文学部って、こういうことをやるんだよね? いいなあ、面白いなあ。やっぱり健康に留意して長生き、その暁には文学だ。2023/06/30
ビイーン
32
「沈黙」の創作秘話から文学の奥の深さを学ぶ。ユーモアを交えて楽しませながら生きる上で大切な事を気づかせてくれた。本書で紹介された本のいくつかは読みたい本に登録した。2021/11/25
-
- 洋書
- Zeroed Out
-
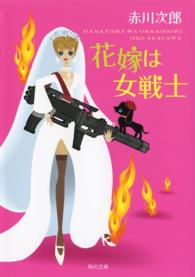
- 和書
- 花嫁は女戦士 角川文庫