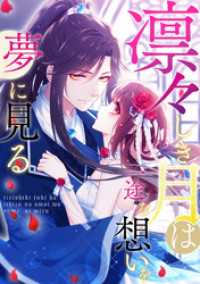内容説明
赤玉ポートワインで莫大な利益を得ながら、危険を冒して日本初の国産ウィスキー製造に取り組んだサントリーの創始者・鳥井信治郎。戦後の経済成長のなか、父親譲りの「やってみなはれ」精神で次々と新分野に挑戦しながら、念願のビール市場参入を果たした二代目・佐治敬三。ベンチャー精神溢れる企業の歴史を、同社宣伝部出身の芥川賞・直木賞作家コンビが綴った「幻のサントリー社史」。
目次
青雲の志について―小説・鳥井信治郎(山口瞳)
やってみなはれ―サントリーの七十年・戦後篇(開高健)
著者等紹介
山口瞳[ヤマグチヒトミ]
1926‐1995。東京生れ。1962(昭和37)年、『江分利満氏の優雅な生活』で直木賞受賞。代表作に『血族』(菊池寛賞)などがある。’63年「週刊新潮」で始まった「男性自身」は、31年間1614回に及ぶ
開高健[カイコウタケシ]
1930‐1989。大阪市生れ。大阪市立大卒。1958(昭和33)年、「裸の王様」で芥川賞を受賞。代表作に『輝ける闇』(毎日出版文化賞)、『玉、砕ける』(川端康成賞)、『耳の物語』(日本文学大賞)などがある
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
123
サントリー宣伝部にいらっしゃったご三方(山口瞳、開高健、柳原良平)のコラボによるサントリーの社史です。山口瞳による日本で初めて国産ウィスキーに取り組んだ鳥井信治郎のはなし、開高健によるビール市場に参入した佐治敬三を中心とした話、さらには柳原によるカットがあり贅沢な本だと思います。このような人材を抱えてベンチャー精神に富んだ会社は面白いですね。2024/02/04
あすなろ@no book, no life.
88
やってみなはれというサントリー。僕は身の程知らずだが、以前未上場だったこの魅力的な会社に実は中途採用応募したことあるぐらい興味ある会社。その閑話休題。お二人のうち、やはり開高氏の久しぶりの粗野に核心を描く文章が好み。天才的な嗅覚と考え抜いた上でのやってみなはれ心情の鳥井氏は、デザインポリシー重視即ち客の買おうという気持ちは安く扱われることを嫌う心情を知っていたり、陰徳あれば陽報ありという姿勢、そして2人の文士を出す社風…。興味深過ぎる。そして鳥井氏の嗅覚で司られた山崎蒸留所には今も原酒が寝ているのである。2018/09/16
kishikan
61
NHKの朝ドラ「まっさん」を見て、日本のウィスキー作りの歴史に関心を持った人ならこの本を読まなければなるまい。といっても、朝ドラは、ニッカでこちらはサントリーの話。それはともかく、なんといっても著者が凄い!サントリー(当時は寿屋)の宣伝部に勤めていた、山口瞳と開高健。直木賞、芥川賞作家のこの二人が、CMのコピーを書いていたのだから、そりゃCMに味があるわけだよなぁ、と柳原良平が生んだアンクルトリスのCMを思い出す。まあ、とにかく創業者の鳥井信治郎と二代目の佐治敬三の「やってみなはれ」精神の幻の社史である。2015/07/10
yamatoshiuruhashi
59
サントリーが産んだ山口瞳、開高健、両巨匠によるサントリー社史、らしい。社史というにしては読みやすいのである。創業者鳥井信治郎の部分を山口が書き、2代目佐治敬三を開高が書く。筆致の違いがまた其々の面白さを引き立てている。あれこれと手を伸ばしていながら実は目指すものをしっかりと持ちそこへ粘り強く辿り着こうとする個人の力も素晴らしいものだが、それを共有してしまう社風も凄い。「陰徳あれば陽報あり」と「「やってみなはれ」に押し捲られた一冊だった。2021/08/29
金吾
52
○創始者のバイタリティーや人間を魅了していくすごさがよく伝わります。ウイスキーを普通に飲んでいますが気候の影響がそこまであることは知らなかったので印象に残りました。山口さんの部分が良かったです。2023/01/19