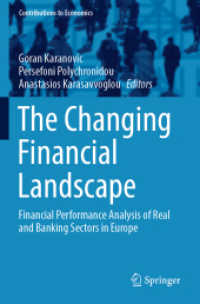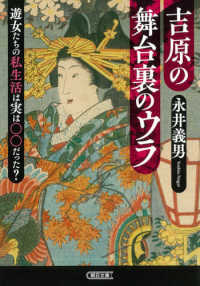出版社内容情報
帝大卒の文部官僚として生きた無口な父と、戦後育ちの3人の娘。平凡な家庭の歳月を「リア王」に重ね、「昭和」を問う傑作小説。
帝大出の文部官僚である砺波文三は、妻との間に3人の娘をもうけた。敗戦後、文三は公職追放の憂き目に逢うが、復職の歓びもつかの間、妻はがんで逝く。やがて姉たちは次々に嫁ぎ、無口な老父と二人暮らしとなった年の離れた末娘の静は、高度成長の喧噪をよそに自分の幸せを探し始めていた。平凡な家族の歳月を、「リア王」の孤独と日本の近代史に重ね、「昭和」の姿を映す傑作長編。
内容説明
帝大出の文部官僚である礪波文三は、妻との間に3人の娘をもうけた。敗戦後、文三は公職追放の憂き目に逢うが、復職の歓びもつかの間、妻はがんで逝く。やがて姉たちは次々に嫁ぎ、無口な老父と二人暮らしとなった年の離れた末娘の静は、高度成長の喧噪をよそに自分の幸せを探し始めていた。平凡な家族の歳月を、「リア王」の孤独と日本の近代史に重ね、「昭和」の姿を映す傑作長編。
著者等紹介
橋本治[ハシモトオサム]
1948(昭和23)年、東京生れ。東京大学文学部国文科卒。イラストレーターを経て、’77年、小説『桃尻娘』を発表。以後、小説・評論・戯曲・エッセイ・古典の現代語訳など、多彩な執筆活動を行う。2002(平成14)年、『「三島由紀夫」とはなにものだったのか』により小林秀雄賞を、’05年『蝶のゆくえ』で柴田錬三郎賞、’08年『双調 平家物語』で毎日出版文化賞を受賞した(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
がらくたどん
Sakie
かふ
ソングライン
...


![An Excellent Exemplar (Uswatun Hasanah) Vol.1: In servitude - In morals - In Manners [The most perfect Human being (pbuh)]](../images/goods/../parts/goods-list/no-phooto.jpg)