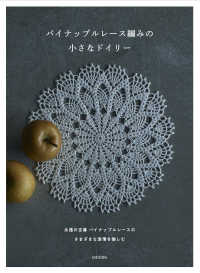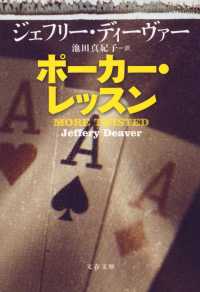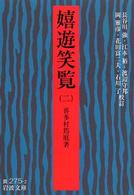内容説明
1980年代後半、金融自由化・国際化の中、地価と株価が急上昇し、日本全体は陶酔的熱狂に浸った。当時、住銀、興銀、野村、山一などの銀行や証券会社と大蔵・日銀、政治家、「バブルの紳士」が繰り広げた狂乱の時代とはなんだったのか?現場を見続けた「伝説の記者」が日本独自の資本主義システムまで議論を深め、「失われた20年」と呼ばれるデフレを招いた原因を捉える“平成”史決定版。
目次
第1章 胎動(三光汽船のジャパンライン買収事件;乱舞する仕手株と兜町の終焉 ほか)
第2章 膨張(プラザ合意が促した超金融緩和政策;資産バブルを加速した「含み益」のカラクリ ほか)
第3章 狂乱(国民の怒りの標的となったリクルート事件;1兆円帝国を築いた慶応ボーイの空虚な信用創造 ほか)
第4章 清算(謎の相場師に入れ込んだ興銀の末路;損失補填問題が示した大蔵省のダブルスタンダード ほか)
著者等紹介
永野健二[ナガノケンジ]
1949(昭和24)年生れ。京都大学経済学部卒業後、日本経済新聞社入社。証券部記者、兜クラブキャップ、編集委員としてバブル期の様々な経済事件を取材する。その後、日経ビジネス編集長、編集局産業部長、日経MJ編集長として会社と経営者の取材を続け、名古屋支社代表、大阪本社代表、BSジャパン社長などを歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
誰かのプリン
15
プラザ合意→円高→土地、株バブル経済と思っていたらどうやらそんな単純ではなかった。政府の円高対策の怠慢、大蔵省の判断ミス、銀行、証券会社の思惑が複雑に絡まって起きた現象だったのですね。2020/05/08
masabi
15
【概要】経済記者が見たバブルの隆盛と破滅、バブルを駆け抜けた人物を記す。【感想】ある問題に対する対処法が別の問題を生み出す種になる経済政策の難しさを感じた。 始めは本業一筋な一人でも真っ当な商売の利益以上の利益を簡単に出せる財テクが周囲で隆盛を極めると誘惑に抗えないのだろう。政治と制度上の不備がバブルの種を蒔き、業務改革を避け容易な道に逃げた銀行証券会社がバブルを膨らませた。 2019/05/13
緋莢
14
図書館本。バブルの事だけでなく、三光汽船のジャパンライン買収事件、幻となったモルガン銀行と野村証券が共同で信託会社を設立など、〝バブル前夜”の出来事も書かれています。<「三菱重工CB事件」と山一証券の死>は齋藤栄功『リーマンの牢獄』でも触れられていた&この本が引用されていました。<国民の心に火をつけたNTT株上場フィーバー>は、詳細は全く分かっていない当時の自分ですら 何となく覚えているのですから、〝フィーバー”してたのでしょう(続く2024/12/02
かんがく
14
平成生まれの私にとっては馴染みのないバブル。そのバブルの中で動いた経営者や官僚たちにフォーカスをあてて問題を明らかにしていく。ある程度、バブルと金融の基礎知識が無いとやや読みづらい。ただ、バブルは証券会社と不動産会社が悪いという一般論に疑問を呈し、バブルを日本型資本主義の限界、第二の敗戦と捉える著者の意気込みは伝わってきた。経済、金融についてより学び、現代日本に分析を重ねていく必要を感じた。2019/07/26
Francis
10
1980年代から1990年代の日本のバブル経済の総括本。私もまさにバブル世代であの頃は学生でもスキーに行くとか車を持つのが当たり前という恐ろしい時代だったのだが、そんなことが長続きするはずもなく1991年を境にあっけなくバブル経済は崩壊、失われた20年に突入してしまう。他の書評では難しいという声が多いが経済学部出身で今も経済学に関心を持っている私には面白く読めた。最後の章でバブル経済を止めた当時の日本銀行総裁三重野康さんが出てくるが、私が卒業する前の年に母校中央大学に講演に来られたことを思い出した。2019/05/11


![[図説]世界の外食文化とレストランの歴史](../images/goods/ar2/web/imgdata2/45620/4562073403.jpg)