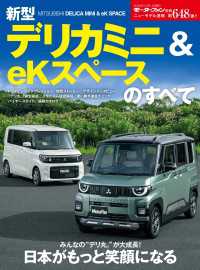内容説明
学問だけを生きがいとしている一郎は、妻に理解されないばかりでなく両親や親族からも敬遠されている。孤独に苦しみながらも、我を棄てることができない彼は、妻を愛しながらも、妻を信じることができず、弟・二郎に対する妻の愛情を疑い、弟に自分の妻とひと晩よそで泊まってくれとまで頼む…。「他の心」をつかめなくなった人間の寂寞とした姿を追究して『こころ』につながる作品。
著者等紹介
夏目漱石[ナツメソウセキ]
1867(慶応3)年、江戸牛込馬場下(現在の新宿区喜久井町)に生れる。帝国大学英文科卒。松山中学、五高等で英語を教え、英国に留学した。留学中は極度の神経症に悩まされたという。帰国後、一高、東大で教鞭をとる。1905(明治38)年、『吾輩は猫である』を発表し大評判となる。翌年には『坊っちゃん』『草枕』など次々と話題作を発表。’07年、東大を辞し、新聞社に入社して創作に専念。『三四郎』『それから』『行人』『こころ』等、日本文学史に輝く数々の傑作を著した。1916年、最後の大作『明暗』執筆中に胃潰瘍が悪化し永眠。享年50(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 3件/全3件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
533
1912年12月から翌13年11月まで朝日新聞に連載されたのが初出。研究者の間での評価は知らないが、読者として読む限りは幾分かの不満が残る。すなわち、内容からすれば未完ではないのか、との疑問がそれである。二郎の結婚問題にしても、嫂の直との問題、また兄の一郎との確執など、そのいずれもが解決しないままである。また、末尾に置かれたHからの手紙で終わることも唐突の感を免れない。読者は当然に二郎の物語として読むことになるが、彼は初期三部作の三四郎を思わせる。また、一方で手紙で終わる結末は次の『こころ』を予感させる。2021/02/24
ehirano1
199
高い知性故に終始何事も考え過ぎを拗らせた兄貴の話はかなり奥が深かった。幸福になりたいがために幸福の研究を只管積み重ねても幸福は依然として対岸にあった、という件は兄貴に同情したくなります。一方で、兄貴には何が欠けていたのか?何が必要だったのか?そんなことを読後にふと考え、ひょっとすると、小林秀雄の『信ずることと知ること』が一助になるかもしれないと思いました。2025/12/20
まさにい
189
この話の主人公を兄の一郎とみるとき、一郎を繊細すぎると一言で言っていいのであろうか。僕は知ってしまったものの苦悩と捉えた。知らなければ幸福というものを研究することなく、ありのままの物事を受け入れることができるが、『幸福』とは何かを追及する能力があるばかりに思い悩んでしまう。文中に出てくる『絶対的相対』という概念。キリスト教という一神教を知ってしまったがゆえに、仏教の『相対性』と相いれず、真理としての『幸福とは何か』に思いに悩んでしまう。文中最後に出てくる『所有』という概念は無心の境地、ということなのだろう2016/12/05
Major
148
一つ一つの作品を読む度に、漱石の思想に対する関心は深まるばかりであるが、殊に『行人』について僕自身は前頭葉全体が打ち震えるばかりの感動を覚えた。明らかに前期三部作とは趣が違う。敢えて登場人物を凌駕してまで、思想家としての漱石が顔を出してくるのだ。文学的表現のレヴェルで言えば、あれほど批判していた自然主義の手法と理論を部分的に用いている。しかし、用いてできあがった作品は自然主義作品とはやはり一線を画して、漱石が目指した新しい日本文学の端緒を開くものになっているように思う。 3つのコメントへ続く2017/09/02
優希
147
孤独を描ききった作品だと思います。繊細すぎる知識人の苦悩の物語でした。学問だけが生きがいの一郎にとって妻に理解されず、家族矢親戚からも疎遠にされているのはかなりの苦悩だったでしょう。「他の心」をつかめない心の苦しみは、漱石の心の叫びだったのかもしれません。最後の手紙には息をすることもできないような辛い思いが詰まっていました。考えることが苦しみを背負うことに通じる痛みが伝わってきます。2015/09/22