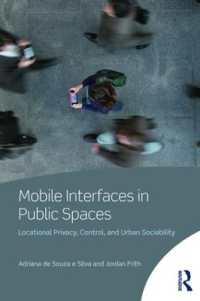出版社内容情報
現代の愛の不毛はこの作品からはじまった。自意識が強く内省的な男と、自由で積極的な女。漱石の男女観を見事に結実させた恋愛小説。
誠実だが行動力のない内向的性格の須永と、純粋な感情を持ち恐れるところなく行動する彼の従妹の千代子。愛しながらも彼女を恐れている須永と、彼の煮えきらなさにいらだち、時には嘲笑しながらも心の底では惹かれている千代子との恋愛問題を主軸に、自意識をもてあます内向的な近代知識人の苦悩を描く。須永に自分自身を重ねた漱石の自己との血みどろの闘いはこれから始まる。
1 ~ 3件/全3件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まさにい
166
明治時代の高等遊民の悩み。これが漱石の多くの小説の主題のようだ。文明開化とは、資本主義的合理主義のこと。これを上滑りに理解して出世、拝金主義に走れば悩みはない。しかし、これを本当に理解しようとすれば、日本人の持っている感覚(感性というのか美徳というのか)と合わず、悩むことになる。漱石に出てくる多くの高等遊民の悩みは後者ということになる。この時代の高等遊民はそれなりの資産があるからいいが、現在の高等遊民は、高等貧民である。しかも資本主義自体に疑問がある時代において、自我を通して生きていくのは辛いものがある。2016/11/05
のっち♬
163
修繕寺の大患と周囲からの孤立を経て著者は原点である写生文にたち帰ることに。その内容は恋愛や親子関係をガジェットに内向的な青年の苦悩を遠景的眼線で描くという自己分析的なもの。浪漫趣味の聞き手が善悪に無関心な探偵という点も彼らしい。自然派にも浪漫派にも背を向けた"自分が自分である"宣言は作品のテーマとも密接な関係にある。須永の違和感は時代状況、恋愛・親子関係に整理を試みても解消される気配が見られず、実存的なものへと遡行していく。「考えずに観る」ことは神経症が児戯的所作となって現れた人間なりの再生への第一歩だ。2022/12/19
優希
160
短編のような形をとりながら、長編小説として成り立っている、雑文的な小説という印象を受けました。軸になるのは自意識の強い内向的な須永と自由で積極的な千代子の恋愛模様。こういう男女の関係は現代にも通じるような気がしました。主人公と語り手が別になっているのも面白いところです。敬太郎を語り手にすることで、少し突き放した視点だからこそ、煮え切らない恋愛模様を味わうことができるのだと思います。高等遊民ならではの苦悩は答が出ない不器用さを感じました。これは新しい日本人としての姿なのかもしれません。2015/10/06
ちくわ
123
『こころ』から読み始めた自分にとって後期三部作最後の作品となった。やや暗い他二作品と比べ漱石らしいコミカルさもあり、個人的には好みだ。ただ通読中はずっと取り留めの無い感覚に包まれ、漱石が何を伝えたいのか判然としなかった。やっと最後の『結末』で少しだけ理解に至る。人夫々に感想があるだろうが、自分はこう考えた。例えば読書は素敵な趣味だが、知識を得るだけでは敬太郎と同じ傍観者のままだ。知識は使ってこそ活きると認識し、少しでも行動に移して現実世界を拡げてみたい!…と思っていたら、もう彼岸(3/23)は過ぎていた。2024/04/01
Kajitt22
118
修善寺の大患後の漱石は、余裕が出てきたのか言い訳から書き出している。連作短編集構想はまさにその通りで、一長編として十分楽しめた。探偵としての尾行劇、登場人物の種明かし、海辺の避暑地での出来事、終局での深い人間観察等、ミステリータッチさえ感じさせる物語。漱石全作品読破が頭の片隅に浮かんできた。2018/01/16
-

- 電子書籍
- はたらく魔王さま!(12) 電撃コミッ…