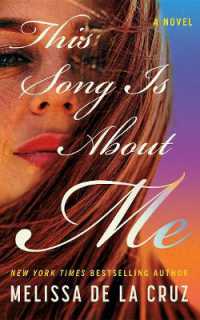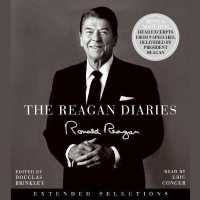出版社内容情報
太宰文学のうちには、旧家に生れた者の暗い宿命がある。古沼のような“家”からどうして脱出するか。さらに自分自身からいかにして逃亡するか。しかしこうした運命を凝視し懐かしく回想するような刹那が、一度彼に訪れた。それは昭和19年、津軽風土記の執筆を依頼され3週間にわたって津軽を旅行したときで、こうして生れた本書は、全作品のなかで特異な位置を占める佳品となった。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
358
長い助走の果てに、最後になってついに太宰が本当に語りたかったことが語られる。言うまでもなく「たけ」との何年ぶりかの再会がそれである。逆説的なのだが、太宰自身が何も語れないところに我々は共感し、涙する。初期の太宰は『晩年』をはじめ、「道化」を自己の含羞の隠れ蓑として作品を書いてきたし、また戦後は『斜陽』や『人間失格』など、新たな地平に踏み出すのだが、この作品は、ちょうどその狭間にあたっている。ここには「道化」もないし、ことさらな仮構もまた見られない。ほんとうに珍しくも「素」の太宰の姿を見ることができるのだ。2012/08/24
ehirano1
254
著者の明部というか、こんなに愛しくも暖かい部分に触れることが出来たことは僥倖でした。たけとの再開のシーンは何故か読んではページを戻ってまた読んでの繰り返す始末で、とても好きなシーンです。2024/10/21
れみ
209
太宰が故郷の津軽を旅して書いた風土記的作品。歴史について書かれた部分はちょっと難しかったけど鬱々とした所がありつつも最後のたけさんとの再会のところや行く先々での様々な人々とのエピソードに心が温かくなったり思わず笑ってしまったりぐっと来たり共感する部分があったり…とても好きな感じだった。Mさんの「卵味噌だ。卵味噌だ」で終わる疾風怒濤の接待が超可笑しくて大好きだなあ。2015/10/21
新地学@児童書病発動中
161
太宰治が故郷の青森を旅した時の旅行記。彼の小説によく出てくる自己憐憫や自己韜晦はなくて、明るく伸びやかなトーンが作品を支配しており、読んでいると晴れ晴れとした気持ちになる。反逆者だった太宰が世間と和解した作品と言えるかも。故郷の風景や人々を描く筆は精彩を帯びていて、美しい日本語を読む喜びを与えてくれた。乳母との再会を描くラストはやはり泣ける。軍部に遠慮したような文が出てくるが、案外皮肉なのではと思った。軍部に左右されない庶民の生活がここにある、という主張が最後の運動会の場面にこめられている気がした。2014/05/29
yoshida
154
太宰治が津軽風土記執筆のため、故郷の津軽を旅する。戦中の昭和19年。足はゲートル巻き、好きな酒も配給であるが3週間の旅は平和であった。何より、家庭も個人的にも充実しており朗らかさを感じる旅であった。太宰治と言えば肥大した自意識や無頼の印象があるが、彼の生の人間味を感じとれる。懐かしい人々との再会。とにかく、酒を飲む。朝から飲むこともしきり。酒量があるので、朝飲んでも寒いと酔いも覚める。酒が飲めなければ太宰ではあるまい。流行作家への賛辞への嫉妬も人間味ある。子守のたけとの再会が頂点。最後の文が白眉である。2020/07/26
-
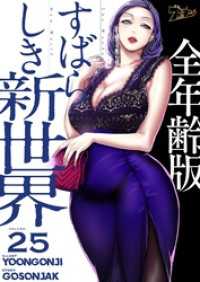
- 電子書籍
- すばらしき新世界(全年齢版)【タテヨミ…
-
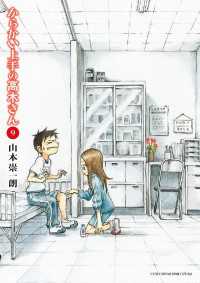
- 電子書籍
- からかい上手の高木さん(9) ゲッサン…