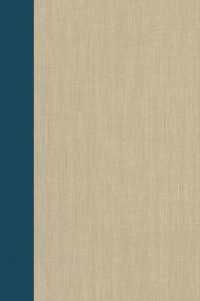出版社内容情報
戦前の〈第一の授業〉、戦後の〈第二の授業〉ではない、授業改革を迫る〈第三の授業〉とは何か。授業に真剣に取り組む教師へ贈る〈新しい授業〉へのアドバイス。
教師主導型の授業から“子ども自らが学ぶ”授業へ……明治いらいの授業、さらには戦後の授業を経て、21世紀をめざす授業はいかにあるべきかを、多年「学び方教育」の研究実践にたずさわってきた著者が、その考え方と具体的な授業記録をもとに、若い教師にもわかりやすく説いた書。生涯学習の時代に、自己教育力を子どもに身につけさせる“第三の授業”こそ、いま求められる授業といえよう。
内容説明
戦前の“第一の授業”さらに戦後の“第二の授業”では、これからの時代を生きる子どもを育てることはできない。自ら学ぶ子を育てる授業こそ〈第三の授業〉である。それはどんな授業か?巻末に授業記録と解説を併載。
目次
1 第一の授業がなぜ
2 第二の授業のどこに
3 いまなぜ第三の授業を
4 「とえらる学習」をこう育てる
5 「たしかめる学習」をこう育てる
6 「ひろげる学習」をこう育てる
7 学習の個別化・個性化
8 学習指導案・授業・そして評価
9 授業に子供が育つとき