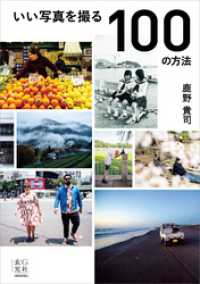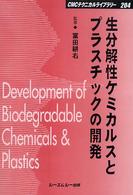出版社内容情報
生きる力が、子どもを救う??。教育界の重鎮が、知識偏重、学歴信仰の現行教育システムにメスを入れ、21世紀に向けた教育の根源的なあり方を展望します。
生活が豊かになった反面、「息苦しさ」にあえぐ現代の子どもたち。いじめや不登校、非行や自閉、過熱する受験戦争など、各種の教育病理が多発、深刻化している。それは子どもたち自身が「生き方」を探しあぐね、「生きる力」さえ失っていることを物語ると同時に、教師には適切な「生き方」の指導ができないという悩みをもたらす。世間からは学校での「生き方」指導の不在や失敗への攻撃が激しくなる。 就職や進学、偏差値や成績、自分の利益や瞬間の快楽だけにしか関心をもたない「生き方」をする人間を大量につくってきた教育の「在り方」、さらには日本社会の「生き方」「在り方」が問われている。そんな中で、昨年六月、中央教育審議会は、子どもたちに「生きる力」と「ゆとり」を、と強力に打ち出した。いま「生きる力」??主体的に学習・判断し、行動する力??をどう獲得するか、「人間らしさ」や「思いやり」を育む「心の教育」は、どうしたら可能なのかを徹底考察する。そして硬直化した教育の考え方に鋭くメスを入れ、二十一世紀に向けた教育の根源的なあり方を展望する。
内容説明
教育界の重鎮が、時代の変化の中でゆらぐ子どもの心をみつめ、教育の再生を提示する。中央教育審議会は、子どもたちに「生きる力」と「ゆとり」を、と強力に打ち出した。いま「生きる力」をどう獲得するか。また、「人間らしさ」や「思いやり」を育む「心の教育」は、どうしたら可能か。知識偏重、学歴信仰の現行教育システムにメスを入れ、二十一世紀に向けた教育の根源的なあり方を展望する。
目次
第1章 「生きる力」探求の視点―ライフの分析(「生きる力」指導のわく組み;生命への畏敬 ほか)
第2章 自己教育力―原点としての自己教育(教育力の限界;自己教育の概念 ほか)
第3章 ゆらぐ子どもの「生き方」―子どもの世界(見えにくい子ども;ゆたかさの中の子ども ほか)
第4章 求められる「心の教育」―「息苦しさ」からの解放(「心の教育」とは;「人間らしさ」 ほか)