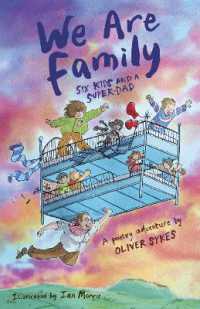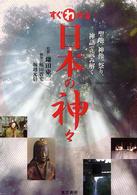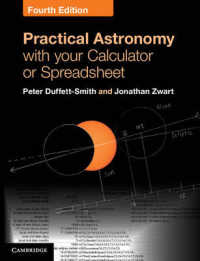出版社内容情報
合理的でムダがない江戸の暮らしに学ぶ
原発はおろか、電気そのものがなかった江戸時代。百万都市・江戸を支えたのは、太陽エネルギーを徹底的に使いこなす資源循環システムだった。江戸の人々は、ムダなく、リサイクルに徹して暮らした。本当に必要なもの以外は持たず、また求めようともしなかった。
月と太陽の動きで時と季節を知る。夕方までに仕事を終えれば照明は要らない。水力を動力源として活用し、燃料は木炭と薪を使った。一反から無駄なく裁断される着物は洗濯も仕立て直しも容易。木綿の着物や浴衣は傷んだら座布団やおむつ、雑巾に使い、最後は焚き付けに。その灰は畑の肥料になった。日用品は何度も直して使い、いよいよ使えなくなれば回収・再生した。冷蔵庫がないかわり、棒手振りをはじめとするさまざまな行商人が旬の食材を長屋まで売りに来た。江戸の長屋は上水道・トイレ完備で、家賃は安かった。大家は民間人でありながら、江戸の行政や治安も担った。
このような江戸の人々の生き方は自然にも人にも優しく、じつは「しあわせ」だったのではないか。今日まで続く江戸ブームの指南役が、具体例と豊富な図版でわかりやすく解説。満ち足りた人生を送るためのヒントが満載。
内容説明
日の出前に起き、日没までに仕事を終えれば照明要らず。狭い長屋暮らしゆえに持ち物は少ない。冷蔵庫はないから、旬の食材しか食べない。修理を重ねて使えなくなった日用品は回収され、再生された。屎尿も集められて畑の肥料になった。太陽エネルギーと、その恵みで育った天然素材を有効に活用し、徹底的なリサイクルが基本であった江戸の生活は、自然と自分に優しく、じつは「しあわせ」だったのではないか―江戸研究の碩学が「指南」する、生き方に役立つヒントが満載。
目次
第1章 暦―太陽が教えてくれた季節
第2章 エネルギー―最大の動力源は水
第3章 着る―無駄なく長く使う
第4章 食べる―旬の食材と外食産業
第5章 住む―上水道、トイレ完備の長屋暮らし
第6章 日用品―使えなくなっても捨てずに回収
第7章 社会―大工と刀鍛冶が人気職業
第8章 流通と交通―馬力と人力を使い分ける
著者等紹介
石川英輔[イシカワエイスケ]
1933年、京都市生まれ。作家・江戸文化研究家。国際基督教大学・東京都立大学理学部をともに中退。1979年、『大江戸神仙伝』(講談社)で作家デビュー(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
sun
れどれ
antonio
めっちー
kamekame