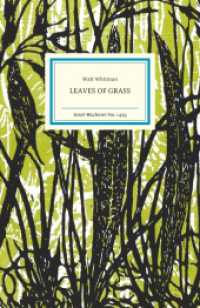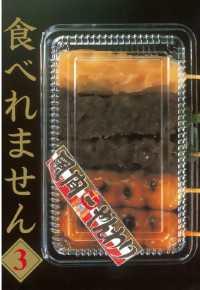出版社内容情報
お役所の作った「変なルール」が国を壊す!
役所・官僚による「規制」が、国民の利益を損ない、企業の成長やビジネスチャンスを妨げていることを、わかりやすく明らかにしていく。
・なぜ日本の電気料金はアメリカの2倍なのか?
・なぜ「余った電力」を一般市民は買えないのか?
・なぜ散髪屋の定休日は地域ごとに一緒なのか?
・なぜ日本のビールをアメリカで買ったほうが安いのか?
・なぜ薬のCMは最後に必ず「ピンポン」と鳴るのか?
・なぜ学校の階段には必ず「踊り場」があるのか?
・なぜ日本の公道で「セグウェイ」が走っていないのか?
・なぜラブホテルに「使われない食堂」ができるのか?
答えは「規制」があるから。様々な業界での、役人たちの手練手管を詳細解説。
これまでの官僚・霞が関批判は「天下り」や「ムダ遣い」「国家I種キャリアの傲慢」に関するものがほとんどだった。しかし、そうした現象が起きる原因、役所の権限の源、となるのは「規制」である。「規制」は非常にわかりづらい悪文で書かれているので、役人の“レトリック”がわからないと、読み解けない。元経産省キャリア官僚の著者が、日本の津々浦々にまで浸透し、この国をダメにする規制の数々に、切り込む。
【編集担当からのおすすめ情報】
本書を読むとわかることは2つ。
1.この国ではお役所の「規制」によって、本当に細かく、いろんなことが決められている。
2.それら「規制」のせいでたくさんの困ったことが起きている。
身の回りの事例から説き起こし、わかりやすく問題点を解説。たくさんの“豆知識”を仕入れながら、「規制」を知り、お役人に騙されない思考を身につけるための、絶好の入門書。
はじめに
第I部 初級編 日常生活に潜む「規制」
第1章 学校のカイダン--なぜ学校の階段には必ず「踊り場」があるのか?
第2章 学校のカイダン2--それでもダメ教師はクビにならない!
第3章 カットできないしがらみ--理髪店がどこも「月曜定休」の理由
第4章 左党のしょっぱい話--なぜ日本のビールをアメリカで買ったほうが安いのか?
第5章 食い物にされる食の安全--「ひやむぎ」と「そうめん」の境目は超厳密だった!
第6章 電気行政の暗闇--なぜ日本の電気料金はアメリカの2倍なのか?
第II部 中級編 ビジネスの邪魔をする「規制」
第7章 アナログな決まり--なぜケイン・コスギはピンチの後にリポビタンDを飲むのか?
第8章 道路の落とし穴--なぜ運転免許は5年で更新しなければならないのか?
第9章 値下げにブレーキ--格安タクシーがデフレなのに値上げを強制されている
第10章 トマる新ビジネス--ラブホテルとビジネスホテルの境界線はどこにある?
第11章 クスリのリスク--なぜ風邪薬はコンビニで買えないのか?
第12章 仕分け会議を仕分けする--結論の半分が「検討する」……蓮舫サン、やる気あったんですか?
第III部 上級編 世の中を支配する「規制」
第13章 選挙に受かって罠に落ちる--投票日前に有名政治家とのツーショットポスターが増える理由
第14章 反古にされる保護--なぜ派遣社員が「電話に出るな」と指示されているのか?
第15章 金利規制が縁の切れ目--借金の上限金利は明治時代から変わっていない
第16章 NOと言えない農家--なぜスーパーの売り場のきゅうりは「真っすぐ」なのか?
最終章 おバカ規制はなぜ作られるのか?--「規制の作り手たち」にまつわる規制
おわりに
原 英史[ハラ エイジ]
著・文・その他
内容説明
「不祥事続きの東京電力との契約なんてもうごめんだ」そう思っても、日本では許されない。実は“余っている電力”はたくさんある。でもそれを国民は買えない…。なぜなら「規制」があるからだ。役所・官僚による「規制」の網は、いたるところに張り巡らされている。子供が通う学校、日々の食卓、何気なく見ているテレビ、そして毎日使う電気―各業界での役人たちの“手練手管”をわかりやすく詳細解説。役所の権限の源となる「規制」はどれも難解だが、役人の“レトリック”を知り尽くす元キャリア官僚の著者が、明解に斬る。
目次
第1部 初級編 日常生活に潜む「規制」(学校のカイダン なぜ学校の階段には必ず「踊り場」があるのか?;学校のカイダン2 それでもダメ教師はクビにならない!;カットできないしがらみ 理髪店がどこも「月曜定休」の理由 ほか)
第2部 中級編 ビジネスの邪魔をする「規制」(アナログな決まり なぜケイン・コスギはピンチの後にリポビタンDを飲むのか?;道路の落とし穴 なぜ運転免許は5年で更新しなければならないのか?;値下げにブレーキ 格安タクシーがデフレなのに値上げを強制されている ほか)
第3部 上級編 世の中を支配する「規制」(選挙に受かって罠に落ちる 投票日前に有名政治家とのツーショットポスターが増える理由;反古にされる保護 なぜ派遣社員が「電話に出るな」と指示されているのか?;金利規制が縁の切れ目 借金の上限金利は明治時代から変わっていない ほか)
おバカ規制はなぜ作られるのか?「規制の作り手たち」にまつわる規制
著者等紹介
原英史[ハラエイジ]
1966年東京都生まれ。東京大学法学部卒、米シカゴ大学ロースクール修了。89年通商産業省(現・経済産業省)入省。大臣官房企画官、中小企業庁制度審議室長などを経て、2007年から安倍・福田内閣で渡辺喜美行政改革担当大臣の補佐官を務める。その後、国家公務員制度改革推進本部事務局勤務ののち、09年7月退官。株式会社「政策工房」を設立し、政策コンサルティング業を営む(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
えちぜんや よーた
tolucky1962
Kentaro
sawa
こーき