内容説明
第一級の言語聴覚士が、発達障害や何かの心配がある子どもの「ことば」を育てる暮らしをていねいに紹介。子どもの「特性」を生かしてよく育てるために大切なこと、が明らかになります。
目次
序章 コミュニケーションを願うすべての人へ
第1章 すこやかな育ちを応援する
第2章 ことばの育ちを支えるということ
第3章 特別支援教育と発達障害の子どもたち
第4章 子どもとの向き合い方、歩き方
第5章 STと一緒に「ことば」を育てた家族
第6章 ことばを窓口として人生とつき合う
著者等紹介
中川信子[ナカガワノブコ]
1948年東京生まれ。言語聴覚士。「子どもの発達支援を考えるSTの会」代表。東京大学教育学部教育心理学科、国立聴力言語障害センター附属聴能言語専門職員養成所(現・国立障害者リハビリテーションセンター学院言語聴覚学科)卒業(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
花男
19
コミュニケーションの意欲は受け手が、受けるよという構えを見せてくれてるかにもよるというのは大切だなと気付かされた。購入したい。2022/08/07
シルク
10
ドラえもんのポケットか....?と、この表紙見ると思う(笑)わたくしのこの本の印象と、ドラえもんポケットに対する印象って、かなり近いな~と思う。頼もしい。すげーなと思う。けどなんかヌクヌクと温もりもある、というような。「ことばは発せられた次の瞬間には消えてしまいます。聞き手の脳の中に記憶(把持)されなければ、なかったと同じことです。」(p.150)「『バイバイ』とことばだけで言われた瞬間に、空の飛行機に気を取られていたら、音はまったく聞こえません。」(p.150)こどもにムキーッとなる前に...という本。2020/02/17
gondan
7
★★★★☆ 発達障害についてはさらりと触れられており、メインはあまり知られていない資格である言語聴覚士がどのようなことをするかを解説した本。子どもの発達障害児と奮闘する言語聴覚士の大変さがよくわかる。この本の評価はとても迷った。なぜなら、本書の終わりに「治るのなら病気、治らないから障害。治せないのにセラピストとは」と治せない苦悩について正直に吐露されているからだ。これを正直ととるか、なんだ治せないのかととるか。どちらにせよ、私には衝撃だった。 2012/03/15
読書熊
5
子どもを育てるためには、親も育つこと。大切な視点2023/07/07
ひろか
4
乳幼児健診に関わったことのある人なら、必ずと言ってよいほど、この著者の本は読んでいるはず。子どもの育ちをどのように支えるかというテーマに対し、言語聴覚士としての立場から、説明している。言語聴覚士らしい記述もないわけではないが、特定の職種に関係なく、子どもの発達というものを理解し、関わるかということであろう。発達領域での言語聴覚士が少ないということであり、その啓発もこめられているように思うが、2010/01/11
-

- 電子書籍
- 失恋!やけ酒?まさかの朝チュン!? で…
-

- 電子書籍
- RCmagazine 2022年7月号
-

- 電子書籍
- 【電子版】ヤングアニマルZERO4/1…
-

- 電子書籍
- スクールガール マリエンさん 後編 ス…
-
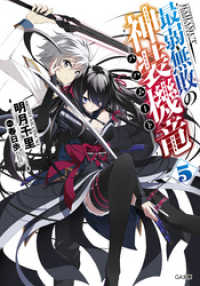
- 電子書籍
- 最弱無敗の神装機竜≪バハムート≫5 G…




