内容説明
近代沖縄の苦悩のなかで生まれた「沖縄学」。その父といわれる伊波普猷に決定的な影響を与えた新潟出身の国語教師・田島利三郎。幕末、西欧諸国の思惑と琉球王国の危機に揺れる時代に滞在したユダヤ人宣教師・ベッテルハイムの葛藤。琉球に源為朝がやってきたという「偽史」はいかにして生まれ、固定化したのか。江戸期の琉球ブームをときあかし、「異国琉球」が「日本」に取り込まれてゆく過程を描く。また沖縄芸能は本土でどう受容されたのかを丹念に追う。刺激的な日本/琉球・沖縄論。
目次
第1章 放浪先生の贈りもの 田島利三郎―「沖縄学」の父・伊波普猷。破天荒な教師との出会いが生む感動的な物語。
第2章 為朝はまた来る?「琉球本」の系譜―歴史とは何か。中国と幕藩体制の日本のはざまで生きる琉球の実像。
第3章 宣教師はご機嫌ななめ バーナード・ジャン・ベッテルハイム―異国船来航に翻弄される琉球。ユダヤ人宣教師の「言葉」の格闘の日々。
第4章 レヴュウになった“琉球” 田辺尚雄/日劇ダンシングチーム―沖縄芸能はいつ、なぜ注目されたか。背景にある「国民意識」の統合とは。
著者等紹介
与那原恵[ヨナハラケイ]
1958年東京生まれ。ノンフィクションライター。「文藝春秋」「エスクァイア」「東京人」「婦人公論」「週刊ポスト」などにルポやエッセイを発表。「朝日新聞」などに書評を執筆(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
翔亀
39
【沖縄28】著者は20年ほど前に、当時の世間を賑わした事件を足で追って新たな視点で問い直すルポを雑誌に連発していて、ルポライターってすごいなあと鮮烈な印象を受けた覚えがある(内容は忘れたけど)。彼女はいつしか、沖縄をテーマにするようになり気になってはいたが、ようやく読んでみた。そして東京生まれの彼女は沖縄二世だったことを知る。■全4章からなる本書は、書名にあるように沖縄の「まれびと」つまり来訪者4人がクローズアップされるが、それにより沖縄史が生き生きと語られているところがミソだ。1章は明治期の沖縄。↓2021/11/25
テキィ
6
切ない2010/09/14
ぷくらむくら
0
薩摩(日本)、中国、海外に囲まれた沖縄のしたたかな戦略が垣間見える。「まれびとたち」というタイトルが秀逸。第三章の宣教師さんはあまりにもせつない。2012/02/08
MrO
0
まあ2010/08/09
やまべ
0
著者の個人的な思いが唐突に出てくるのがちょっと……。2009/08/02
-

- 電子書籍
- 舞妓さんちのまかないさん(28) 少年…
-

- 電子書籍
- 【単話売】推し似の同僚と嘘恋はじめます…
-

- 電子書籍
- 正義なる狂犬の嫁になりました【タテヨミ…
-

- 電子書籍
- 歴史に残る悪女になるぞ 2 悪役令嬢に…
-
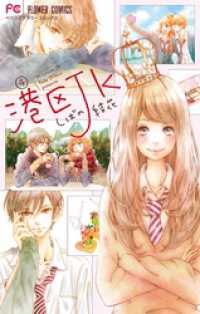
- 電子書籍
- 港区JK【マイクロ】(4) フラワーコ…




