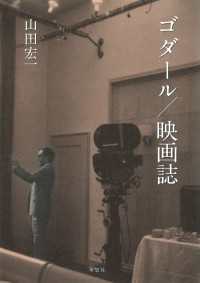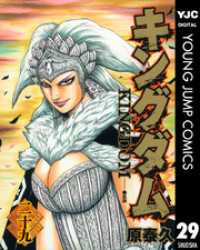出版社内容情報
日本美術という窓から見た西洋美術
古代から現代まで、「同時代性」という観点から、時代ごとに西洋美術と日本美術を比較。それによって、時に不思議なほどの類似点をもち、時に対照的な展開を見せる、また、時に影響し合い、時に遠く隔たる両者の歴史の在り様、そのダイナミズムを、著者独自の切り口によるテーマにそって明らかにしていきます。それによって、各々の美術の歴史を個別に見ていただけではわからない、人の営為としての美術の面白さ、奥深さや豊かさが見えてきます。美術についてのグローバルな理解を追究する意欲作。
『日本美術全集』全20巻の月報にて好評連載「その時、西洋では」を大幅に加筆修正。
内容説明
日本にルネサンスはあったのか?日本美術史という窓を通して眺める西洋美術の歴史。
目次
第1章 先史から古代―オリジナルの誕生(人類最古の美術;奇跡の宗教建築 ほか)
第2章 中世―相違するものと類似するもの(中世絵画の黄金時代;彫刻の終焉と始まり ほか)
第3章 近世―並行する二つの歴史(東西美術の接触;並行する二つの歴史 風俗画とアカデミズム ほか)
第4章 近代から現代―共振する美術(版画の時代;写実の衝撃 ほか)
結 西洋美術と日本美術
著者等紹介
宮下規久朗[ミヤシタキクロウ]
神戸大学大学院人文学研究科教授、美術史家。1963年名古屋市生まれ。東京大学文学部卒業、同大学院人文科学研究科修士課程修了(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
シナモン
105
図書館本。パルテノン神殿が造られた時代、日本は弥生時代、中国は春秋戦国時代だった。ルネサンスの時代、日本は室町時代、雪舟とボッティチェリ、狩野元信とミケランジェロは同時代を生きている。狩野永徳、長谷川等伯が活躍した安土桃山時代、歴史上初めて日本は西洋と接触した。それはカトリック改革による世界戦略の一環だった。伊藤若冲、円山応挙が活躍した江戸中期、西洋ではロココ様式の華やかな宮廷文化の時代だった。専門的で難しいところもありましたが、これだけ分かれば私にとっては大収穫。興味深い一冊でした。2019/11/05
貧家ピー
7
鑑賞した浮世絵と西洋美術の年表を作ったことがあったが、こういった対比は面白い。 日本美術の特徴 美術変遷に建築が大きく関与することがなかった 公共性より私的な性格が強い 工芸との親近性がある 2019/05/16
Mana
5
西洋美術と日本美術を同じ年表で見ていく試み。もともと雑誌の連載だったそうで、一つ一つの章が読みやすい。まあ、昔は全然交流がなかったから特に同じ時代だからといって何か傾向があるわけでもないみたいだけど、美術の流れが分かって面白い。近代になってくるとジャポニズムとかでだんだん関連性が出てくるようになる。2019/06/07
m
4
日本と西洋の美術を時代ごとに比較。お勉強には良いかもしれないが、説明が一辺倒で退屈に感じてしまった。せめてフルカラーだったら良かったのにな。2021/09/30
ganesha
4
西洋美術史が専門の著者が、日本美術史を西洋と比較しつつ考察した一冊。日本美術全集の月報連載を加筆再編集したもの。欧州の歴史と日本美術について改めて知ることがたくさんあり、時間をかけて読了。戦争画とロシア・アヴァンギャルドが興味深かった。神呪寺の如意輪観音を見てみたい(そしてカフェザテラスを再訪したい)2020/05/04