出版社内容情報
江戸時代の全漂流記・取調書をもとに、漂流の原因、漂流時の食物・飲料水・信仰、漂着地など、さまざまな漂流の実態をさぐり、漂流民の見た漂着地(外国)の風俗、情報のほか、漂流民が抱いた世界観・日本観にも迫る。
大黒屋光太夫、ジョン万次郎、ジョセフ彦を代表とする江戸時代の漂流記は多くの人に親しまれている。しかし、鎖国令下の江戸時代には、ほとんどが幕府によって出版を禁止され、外交情報のすべてがにぎりつぶされていた。 本書は、江戸時代の漂流記・取調書のすべてに目を通し、漂流の原因をはじめ、漂流者の食事、飲料水の作り方、信仰など漂流時の日常生活、さらに外国情報、帰還手続き、帰国後の生活など、従来あまりふれられなかった漂流にも焦点をあて、幕府の漂流者・異文化への対応にも迫っている。 漂流記は、近世庶民が初めて異文化と出会い、どのように対応していったかを伝える貴重な資料であり、いまだに異文化とのつきあいが下手だといわれる現代日本人にも、ボーダーレス時代に生きる様々なヒントをあたえてくれる。
内容説明
「世界」を見た近世漂流民。江戸漂流民事情。江戸時代の漂流はなぜ起こり、いかなる漂流を経験したのか。漂流民が諸外国で見てきたものは…。漂流の実態と漂流民の世界観・日本観をさぐる。
目次
第1章 神力丸バタン漂流
第2章 漂流の諸相―督乗丸を中心に
第3章 漂流民の帰国と海外情報
第4章 読まれていた漂流記
第5章 漂流民の見た異人・異国と日本
第6章 漂流民と「日本」
感想・レビュー
-
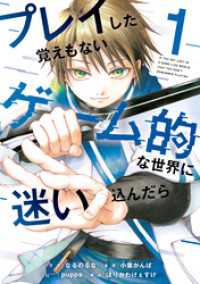
- 電子書籍
- プレイした覚えもないゲーム的な世界に迷…








