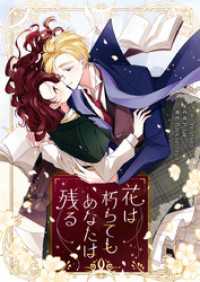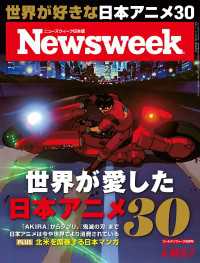出版社内容情報
子供たちを伸ばす場で芥川賞作家がみたもの
現代の学校は、かつての「個性」「自発性」という言葉が影にひっこみ、「和」や「まとまり」という集団主義的な言葉が表を飾っているように感じます。[しかし、ここで紹介している学校は子供たちが積極的に、嬉々として学んでいます。
現代の子供たちに最も欠けているのは、喜んで学ぶという力です。強制ではない積極性が集中力をうみます。そんな意欲的な雰囲気をクラス全体でつくっている学校もありました。
たとえば、授業の前のたった五分間の「百ます計算」でその集中力を難なく達成している教室などです。そのほかにも、辞書引き、小説創作、音読・暗唱、そろばん、右脳開発、コミュニティスクール、中国語等々……。
さまざまなメソッドを駆使してユニークで新しい教育に挑戦している学校は、取材時はエッジ=先端に位置していましたが、今もトップを走っているのです。
【編集担当からのおすすめ情報】
芥川賞作家として小説を書きながら、『「家をつくる」ということ』などノンフィクション作品も定評がある著者が、辞書引き、小説創作、音読・暗唱、そろばん、右脳開発、コミュニティスクール、中国語等々……。さまざまなメソッドを駆使してユニークで新しい教育に挑戦している学校を突撃取材している。
プロローグ ITは子供をほんとうに「伸ばす」のか……12
京都府・京都市「立命館小学校」
三歳から始まる進学問題/教師の個人力はもう古い?
最先端の教育メニュー満載の小学校が誕生/ゴージャスな設備群
第一部 メソッドを選ぶ 勃興する学びの方法
第一章 辞書 六歳から引くべし……24
愛知県・刈谷市立「刈谷南中学校」
三〇〇〇枚の付箋をつける子供たち/ゲーム感覚の国語で目の色が変わる
一年生が六年生を圧倒/書いて書いて書きまくれ!
素朴な「なぜ?」と「はてな帳」/社会性を中学生に
大人が勘ちがいしていること
第二章 そろばん 古くて新しい魔法……39
兵庫県・尼崎市立「杭瀬小学校」
日本初の「そろばん特区」/計算力だけでなく集中力もつく
保護者アンケートで絶賛/あのなにもできなかった子が!
第三章 生活体験 幼児期の必須授業……48
兵庫県・西宮市「レクタス教育研究所」、
東京・青山「こどもの城」幼児体育教室
幼児が描いた「腕のない絵」/なぜ母親は気がつかないのか
「子供より私」の発想/うまく走れない小学生/鬼ごっこすら塾で学ぶ!
第四章 暗算 脳という開拓地……66
神奈川県・横浜市「神林そろあん教室」
なぜ瞬時に暗算ができるのか/みんなおもしろがって熱中する
「泥んこになって遊ぶ子ほど、よく伸びます」
第二部 学校を選ぶ 公立校の底力
第五章 一貫校 公立校復興の狼煙……74
広島県・東広島市「広島県立広島中学校・高校」
鳴り物入りの新設・一貫校/膨大な「シラバス」を読みこむ親
私立を意識した大学受験体制/こんなに本好きがいるとは!
「適正検査」という名の入試問題/なぜ、寄宿希望者が多いのか
第六章 カリスマ校長 「w山V男」という名の教育……91
広島県・尾道市立「土堂小学校」
過激な実験/百ます計算、音読・暗唱
未来へのプレゼント/家庭でやるべきこと
「傷ついていいじゃないですか」/急増した一年生
なぜ学力は低下したのか
第七章 小説創作 子の心をのぞく教育……114
広島県・尾道市立「土堂小学校」
また来なければならない/「特別授業」で涙した女の子
六年生が書いたミニ小説/「一人になりたい」というメッセージ
なぜ勉強をするのか
第八章 コミュニティスクール 総合的な学習の極地……131
京都府・京都市立「御所南小学校」
学校の評判が地価をあげる時代/これぞ本物の総合的な学習
「これ読んでください」といった児童/なぜ本物の出産シーンをみせるのか
ずば抜けて高い「書く力」/総勢九〇名の援軍組織
クラスという聖域を壊す!
第三部 言葉を選ぶ 母語を捨てる
第九章 バイリンガル教育 恵まれた最高の小学校……154
福岡県・太宰府市「リンデンホール小学校」
朝はグッドモーニング! でスタート/わずか六歳の寄宿生
二六人を教師二人で担当する贅沢/校内で田植え、稲刈りができる
中途半端な英語教育は無駄
第一〇章 インターナショナル校 日本のなかの外国……169
東京・池袋「ニューインターナショナルスクール」(幼稚園?中学)
一気呵成に英語で話す娘/学校教育法第一条という壁
教師一人に生徒一〇人/「英語の上達には、まず日本語です」
塾とセットで受験も万全という作戦
第一一章 中国語 隣国の経済成長をにらむ親たち……184
神奈川県・横浜市「横浜山手中華学校」(幼稚園?中学)
ものものしい警備態勢/六年生が先生役で教える
「ふるいにかける」「競争させる」/中国式のスパルタ教育
学力を無視した不合理な差別/これからは英語より中国語
第一二章 国際基準の卒業試験 バカロレアという難関を目指して……199
静岡県・沼津市「加藤学園」(幼稚園?高校)
東京から引っ越ししてまで通わせたい地方校
日本語と英語が飛びかう休み時間
最後は日本語テストでフォロー/文部大臣との直談判
イン・ユア・オウン・ワーズ
後書きにかえて
選ぶ学校、選ばれる教育……216
教育格差の時代なのか/教師はコーディネーターになる?
知を手に入れる場所
藤原 智美[フジワラ トモミ]
内容説明
現代の学校は、かつて目標として掲げられていた「個性」「自発性」という言葉が影に引っこみ、「和」や「まとまり」という集団主義的な言葉が表を飾っているように感じます。しかし、ここで紹介している学校は子供たちが嬉々として学んでいます。現代の子供たちに最も欠けているのは、喜んで学ぶという力です。辞書引き、小説創作、音読・暗唱、そろばん、右脳開発、コミュニティスクール、中国語等々…。さまざまなメソッドを駆使してユニークで新しい教育に挑戦している学校は、取材時はエッジ=先端に位置していましたが、今もトップを走っているのです。
目次
プロローグ ITは子供をほんとうに「伸ばす」のか―京都府・京都市「立命館小学校」
第1部 メソッドを選ぶ勃興する学びの方法(辞書 六歳から引くべし―愛知県・刈谷市立「刈谷南中学校」;そろばん 古くて新しい魔法―兵庫県・尼崎市立「杭瀬小学校」;生活体験 幼児期の必須授業―兵庫県・西宮市「レクタス教育研究所」、東京・青山「こどもの城」幼児体育教室;暗算 脳という開拓地―神奈川県・横浜市「神林そろあん教室」)
第2部 学校を選ぶ公立校の底力(一貫校 公立校復興の狼煙―広島県・東広島市「広島県立広島中学校・高校」;カリスマ校長「陰山英男」という名の教育―広島県・尾道市立「土堂小学校」;小説創作 子の心をのぞく教育―広島県・尾道市立「土堂小学校」;コミュニティスクール 総合的な学習の極地―京都府・京都市立「御所南小学校」)
第3部 言葉を選ぶ母語を捨てる(バイリンガル教育 恵まれた最高の小学校―福岡県・太宰府市「リンデンホール小学校」;インターナショナル校日本のなかの外国―東京・池袋「ニューインターナショナルスクール」(幼稚園~中学)
中国語隣国の経済成長をにらむ親たち―神奈川県・横浜市「横浜山手中華学校」(幼稚園~中学)
国際基準の卒業試験 バカロレアという難関を目指して―静岡県・沼津市「加藤学園」(幼稚園~高校))
後書きにかえて 選ぶ学校、選ばれる教育
著者等紹介
藤原智美[フジワラトモミ]
1955年、福岡市生まれ。フリーランスのライターとして各誌で活躍後、92年『運転士』で第107回芥川賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
yyrn
ラッキー
今Chan
hr