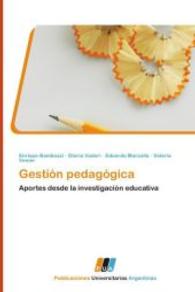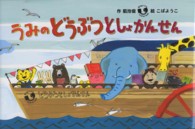出版社内容情報
江戸時代、旅は町人たちの楽しみの一つだった。宿場宿場には、名物の菓子や料理が用意され客を誘っていた。品川のあなご、江の島のアワビ、興津の鯛、鞠子のとろろ汁など当時の名物料理を、江戸時代の旅行記や名所図会などから紹介。
旅の楽しみ方は人によりいろいろあるという。観光もかかせないだろうがその土地の名物といわれるものを食べることも楽しみの一つである。 江戸時代には庶民は旅行などする余裕はなかったとされるが、伊勢講などを組織してほとんど一生に一度の旅行を楽しんだ。彼ら旅人を迎える宿場の人たちも知恵を絞って客寄せに励んだ。よその宿場にないおいしいものを提供するため、素材や技術を磨き名物といわれるものを生み出した。現在でもデパートの催しで駅弁大会は人気があるというのは、江戸時代の名残のようなものだろう。 本書はいまだに残る、名物を提供するお店へのアクセス地図を掲載して、2000年代の弥次喜多気分を味わえるよう配慮したもので、この本片手に東海道を楽しんでいただきたい。
内容説明
名物に旨いものあり東海道。庶民の旅の楽しみはおいしいものを食べること。さて、何がいちばん旨かったか?それを追究、追体験することで、日本の旅の文化史・精神史が浮かび上がってくる。
目次
たべもの東海道(鮫洲のあなご;万年屋の奈良茶と鶴見の米饅頭;江の島の料理と土産物 ほか)
旅の食物史(椎の葉に盛る飯;乾飯に涙;運脚と防人 ほか)
資料(道中唄;東海道宿勢一覧)