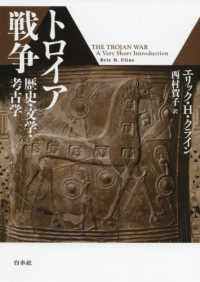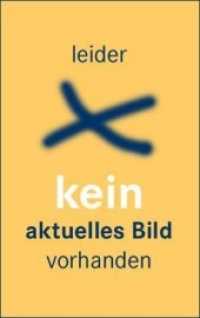出版社内容情報
脳は大別すると、右脳と左脳に分けられ、それぞれが別の機能を持っている。話し言葉と虫の声を聞きわけることができるのはこのためである。評判を呼んだ名著に新原稿を追加したライブラリー版。
●目次 はじめに 日本人の音認知の特徴<リポート> 脳の機能と文化の異質性<シンポジウム> 言語と音楽?音楽の生理的意義?Harmonic brainとInharmonic brain?脳のスイッチ機構の働き? 氏か育ちか ツノダテストで意識下の世界を探る 本書関連のおもな著作一覧 あとがき
内容説明
人間の脳は、言葉と音を聞きわける左脳と右脳に分かれています。しかし、その働きは、言語や民族の違いによって異なるといわれます。脳研究の権威が、脳機能の神秘的な働きをわかりやすく解説します・
目次
1 日本人の音認知の特徴〈リポート〉
2 脳の機能と文化の異質性〈シンポジウム〉
3 言語と音楽―音楽の生理的意義
4 ツノダテストで意識下の世界を探る
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
清水勇
6
1992年発行。著者は、日本人(日本語環境に10歳まで過ごした人)の右脳・左脳の認知方法が、西欧人・中国人・韓国人他とは逆であることをユニークな検査方法で立証。日本人は、論理脳である左脳で母音、感情音、動物・虫他の鳴き声、風・波等の自然音を認知。西欧や中国では人工物と自然物を分ける傾向なのに、何故日本では自然と一体を好むのかが導かれる。鳴き声や自然音に言葉を当てはめる擬態語や擬音語の多さの理由もわかる。著者はその原因を、日本語の母音だけの言葉の多さに着目。又同じ実験で脳の検知機能の精細度の高さも実証。2015/05/21
student_d
2
『右脳と左脳―その機能と文化の異質性』(1982)を文庫化、増補したもの。「視覚と聴覚の神経は交差していて、右耳から入った物の多くは左脳に入る」「西洋人と日本人とで虫の音などの雑音の処理方法の違いがある」「西欧人は、虫の音を楽器と同じように捉え、右脳で処理するが、日本人は、言語と捉え、左脳で処理する」という。この内容は自分にとって衝撃的であった。茂木先生から始まった、「脳科学・脳トレブーム」よりずっと昔に、こうした内容があったとは思わなかった。参考になる。2012/01/03