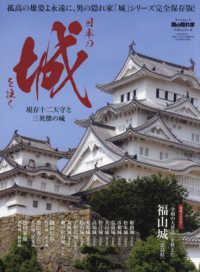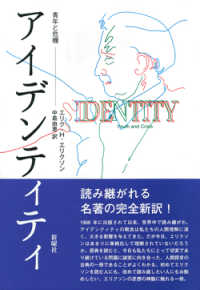出版社内容情報
なぜ、いい人ほど不幸になるのか?
「誰かのため」なら、もっとよく生きられる――。悲しみや不安、悩みの多い人生を生き抜くヒントは「利他」=人のために尽くす生き方にある。
九十歳を過ぎてなお話題作を次々発表し、「青空説法」で数千人の聴衆を魅了し続ける作家・瀬戸内寂聴。京セラ創業者にして日本航空の再建も果たし、八千人を超える塾生を指導する経営者・稲盛和夫。
自ら「利他」を実践し続ける二人が、仏教の教えやユーモアを織り交ぜながら、震災後の苦難を生きる「知恵」と「覚悟」を語り合う。
「気分が楽になった」「勇気が湧いてくる」読者絶賛の傑作対談、ついに文庫化。
解説・阿川佐和子
【編集担当からのおすすめ情報】
多忙を極める著者お二人に対談していただくのは、「奇跡に近い難事」(「あとがき」より)でしたが、実際に対談を重ね、「人間として、いかに生きるべきか」を真摯に語り合った本作品は、今を生きる多くの読者に、勇気と元気を与える内容になっていると思います。
文庫解説は、作家・エッセイストの阿川佐和子さん。著者それぞれに会った際の貴重なエピソードをまじえながら、多くの聴衆を惹きつけるお二人の語りや言葉の魅力について解説しています。
はじめに 稲盛和夫
[震災を経験して]
第一章 今こそ、勇気を
――「千年に一度」の悲しみを乗り越える法――
半年間“寝たきり”になってわかったこと
終戦直後と同じ、逆境を乗り越えるのは強い心
“第二の故郷”東北人の強さを信じる
神様から顔をはたかれたような気がした
「人間の想像力などたかが知れている」という自戒
[逆説の人生観]
第二章 なぜ、いい人ほど不幸になるのか
――どんな悪い世の中もいずれ変わる――
「小善は大悪に似たり」「大善は非情に似たり」
「代受苦」――犠牲者は我々の苦しみを引き受けてくれた
借金で自殺するぐらいなら踏み倒す「不真面目のすすめ」
先に死んでいく者には、生き残る人への「義務」がある
戦災孤児の“かっぱらい精神”にバイタリティを学ぶ
「生生流転」「諸行無常」――絶望から立ち直る知恵
[震災後の生き方]
第三章 「利他」のすすめ
――人は“誰かの幸せ”のために生きている――
震災の死者の名前を書き続ける女性の姿に涙が出た
人に言われなくても、困っている誰かのために働く人がいる
「損得勘定」や「利己主義」が社会を悪くしている
儲からないはずの宗教で、なぜ次々に殿堂が建つのか
人間に本当に必要なのは「目に見えないもの」
己を忘れて他に利する――「忘己利他」という教え
「地獄」と「極楽」の違いは紙一重にすぎない
大事なのは「声に出して」「他人のために」「みんなで」祈ること
「笑いの力」――不幸は悲しい顔が好きで、幸せは笑顔が好き
[新・日本人論]
第四章 日本を変えよう、今
――「小欲知足」と「慈悲」を忘れた日本人へ――
非常時には非常時のルールを導入せよ
“九十年”生きてきて、今ほど贅沢な時代はない
これから求められるのは「忍辱」の精神
今ほど「心」が暗くて悪い時代はない
人に人でなしのことを言うと、自分が苦しい
「母性愛」こそ、お釈迦様の「慈悲」の典型
「子ども手当」に頼らず自分の力で子育てを
「なぜ人を殺してはいけないのか」の答えは理屈抜き
子供にも「家族の死」を見せたほうがいい
[「利他」の実践]
第五章 人はなぜ「働く」のか
――“誰かのために尽くす”ことが心を高める――
最初は嫌でも本気でやれば必ず仕事が好きになる
自分の歳を忘れるぐらい、仕事に惚れ込んでいる
寝食を忘れて働くのは、僧侶の修行に匹敵すること
なぜ「七十八歳」「無給」でJALの会長を引き受けたか
会社を変えるのは「テクニック」ではなく社員の「心」
エリート意識の壁を取り払った「会費千円」の飲み会
「目が覚めた」という社員が一人出てくれば周囲に伝播する
ビジネスの決断も「人間としてどうなのか」が基本
社員がマニュアルではなく自分で考えて働き始めた
[生と死のあいだ]
第六章 「天寿」と「あの世」の話
――「生老病死」の四苦とどう付き合うか――
「諸行無常」だから、震災後の日本にもいいことが起きる
「歳をとるほど生きづらい…」日本人は長生きしすぎる
大きな病気にならずに済んでいるのは「守られているから」
「寂聴極楽ツアー」なら「あの世」に行くのも怖くない
おわりに 瀬戸内寂聴
解説 阿川佐和子
【著者紹介】
1922年徳島県生まれ。東京女子大学卒業。57年「女子大生・曲愛玲」で新潮社同人雑誌賞受賞。63年「夏の終り」で第2回女流文学賞受賞。73年に中尊寺で得度受戒。92年「花に問え」で谷崎潤一郎賞受賞、2001年「場所」で野間文芸賞受賞。06年に文化勲章を受章。著書に「現代語訳源氏物語」「秘花」など多数。
内容説明
「誰かのため」なら、もっとよく生きられる―。悲しみや不安、悩みの多い人生を生き抜くヒントは「利他」=人のために尽くす生き方にある。九十歳を過ぎてなお話題作を次々発表し「青空説法」で数千人の聴衆を魅了し続ける作家・瀬戸内寂聴。京セラ創業者にして日本航空の再建も果たし八千人を超える塾生を指導する経営者・稲盛和夫。自ら「利他」を実践し続ける二人が、仏教の教えやユーモアを織り交ぜながら震災後の苦難を生きる「知恵」と「覚悟」を語り合う。「気分が楽になった」「勇気が湧いてくる」読者絶賛の傑作対談、ついに文庫化。
目次
第1章 震災を経験して・今こそ、勇気を―「千年に一度」の悲しみを乗り越える法
第2章 逆説の人生観・なぜ、いい人ほど不幸になるのか―どんな悪い世の中もいずれ変わる
第3章 震災後の生き方・「利他」のすすめ―人は“誰かの幸せ”のために生きている
第4章 新・日本人論・日本を変えよう、今―「小欲知足」と「慈悲」を忘れた日本人へ
第5章 「利他」の実践・人はなぜ「働く」のか―“誰かのために尽くす”ことが心を高める
第6章 生と死のあいだ・「天寿」と「あの世」の話―「生老病死」の四苦とどう付き合うか
著者等紹介
瀬戸内寂聴[セトウチジャクチョウ]
1922年徳島県生まれ。作家・僧侶。57年『女子大生・曲愛玲』で新潮社同人雑誌賞。61年『田村俊子』で田村俊子賞。63年『夏の終り』で女流文学賞。73年に岩手・中尊寺で得度。87年より天台寺住職に就任し、無料の青空説法を始める(2005年以降、名誉住職)。92年『花に問え』で谷崎潤一郎賞。96年『白道』で芸術選奨文部大臣賞。2001年『場所』で野間文芸賞。06年に文化勲章、国際ノニーノ賞。08年に坂口安吾賞受賞
稲盛和夫[イナモリカズオ]
1932年鹿児島県生まれ。経営者。59年に京都セラミック(現・京セラ)を設立。社長、会長を経て、97年より名誉会長を務める。84年に第二電電(現・KDDI)を設立し、会長に就任。2001年より最高顧問。2010年に日本航空(JAL)会長に就任し、再建を果たす。2013年より名誉会長。このほか84年に稲盛財団を設立し、「京都賞」を創設。毎年、人類社会の進歩発展に功績のあった人々を顕彰している。また、経営塾「盛和塾」の塾長として、経営者の育成に心血を注いでいる。97年に京都・円福寺で得度(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
フジマコ
みねたか@
Shohei I
Mark X Japan
三上 直樹
-
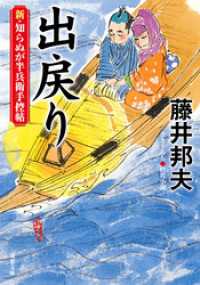
- 電子書籍
- 新・知らぬが半兵衛手控帖 : 19 出…
-

- DVD
- 鉄人28号 DVD-BOX 2