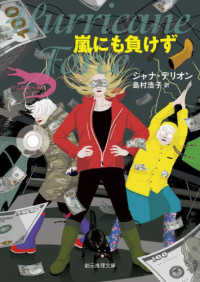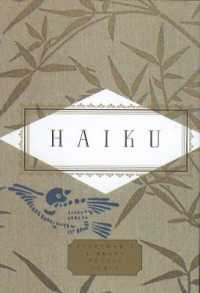- ホーム
- > 和書
- > 教養
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
出版社内容情報
絶体絶命でも捕鯨を続ける男たちの群像
反捕鯨団体の過激な妨害活動、国際社会からの批判――日本の捕鯨は、幾度も障壁にぶつかってきた。
シー・シェパードが妨害を過激化させた2000年代後半。著者は調査捕鯨船に同行取材し、若手船員たちの情熱や葛藤を目の当たりにする。
しかし、日本が調査捕鯨で積み重ねたデータは、国際社会では認められなかった。2019年、日本はIWC(国際捕鯨委員会)を脱退し、200海里内での「商業捕鯨」に舵を切る。それは同時に、かつて船員が奮闘した「南極海」「北西太平洋」での捕鯨が終焉することを意味していた。
奇しくも2019年に亡くなった「クジラ博士」は、南極海捕鯨の終焉を誰よりも惜しみ、こう言った。
「まさに“けいげいのあぎとにかく”ですね」
けいげいとは雄クジラと雌クジラ、あぎとは鰓(エラ、アゴ)のこと。クジラに飲み込まれそうになったが、アゴに引っかかって助かった――。そんな絶体絶命な状況のなか、いかにして日本の捕鯨は続いてきたのか?
およそ15年の時を経て、著者は再び捕鯨船に乗船取材。若手から中堅になった捕鯨船員たちと、「クジラ博士」の歩みを通して、捕鯨業界の「再起への航跡」を辿る。
内容説明
過激な妨害活動、国際世論の批判―それでも捕鯨を続ける男たちの群像。
目次
第1章 クジラ捕りの肖像(写真を撮る鯨探士;花形と女房役;チーム・キャッチャーボート;大包丁と家族)
第2章 論争の航跡(科学と政治のはざまで―クジラ博士の苦悩;商業と調査のはざまで―ベテラン船員の葛藤;反捕鯨団体の論理;南極海を遠く離れて;悲しい失敗;クジラ博士の遺言)
第3章 捕鯨の未来(商業捕鯨の生肉;歯車のプライド;技術の継承;青春の日新丸)
著者等紹介
山川徹[ヤマカワトオル]
1977年、山形県生まれ。ノンフィクションライター。東北学院大学法学部卒業後、國學院大學二部文学部史学科に編入。2010年、北西太平洋の調査捕鯨を取材した『捕るか護るか?クジラの問題』(技術評論社)を出版。2020年、『国境を越えたスクラム ラグビー日本代表になった外国人選手たち』(中央公論新社)で第三〇回ミズノスポーツライター賞最優秀賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
hitotak
しーたか
おぎゃ
林芳
-

- 電子書籍
- 百花宮のお掃除係 7 特装版【短編小説…